 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
後漢の漢安年中、会稽上虞に曹娥といふ少女がいた。その父の名を曹 といふ。漢安二年、 といふ。漢安二年、 が伍君(子胥)の神を迎へるために、濤に逆つて上つたところ、水沒して死に、その屍が浮かなかつた。時に十四であつた娥は悲歎のあまり澤畔に哀吟すること十七日、遂に自ら江に投じて死し、五日の後に父の屍を抱いて浮かび出でたといふ。時人その志を哀れみ、縣長の度尚が祭を設け碑を建てた。後に漢末の亂を避けて呉に至つた蔡 が伍君(子胥)の神を迎へるために、濤に逆つて上つたところ、水沒して死に、その屍が浮かなかつた。時に十四であつた娥は悲歎のあまり澤畔に哀吟すること十七日、遂に自ら江に投じて死し、五日の後に父の屍を抱いて浮かび出でたといふ。時人その志を哀れみ、縣長の度尚が祭を設け碑を建てた。後に漢末の亂を避けて呉に至つた蔡 がこの碑を讀み大いに感心し旁に「黄絹幼婦外孫齏臼」の八字を題した。世説新語・捷悟に「魏武曹娥碑の下を過り、楊修從ふ。碑背上に題して黄絹幼婦外孫齏臼の八字を作るを見る。魏武修に謂ひて曰く、解せしや不やと。答へて曰く、解せりと。魏武曰く、卿未だ言ふべからず、我が之を思ふを待てと。行くこと三十里にして、魏武乃ち曰く、吾已に得たりと。修をして別に知る所を記せしむ。修曰く、黄絹とは色絲なり、字に於て絶と爲す、幼婦とは少女なり、字に於て妙と爲す、外孫とは女子なり、字に於て好と爲す。齏臼とは受辛なり、字に於て がこの碑を讀み大いに感心し旁に「黄絹幼婦外孫齏臼」の八字を題した。世説新語・捷悟に「魏武曹娥碑の下を過り、楊修從ふ。碑背上に題して黄絹幼婦外孫齏臼の八字を作るを見る。魏武修に謂ひて曰く、解せしや不やと。答へて曰く、解せりと。魏武曰く、卿未だ言ふべからず、我が之を思ふを待てと。行くこと三十里にして、魏武乃ち曰く、吾已に得たりと。修をして別に知る所を記せしむ。修曰く、黄絹とは色絲なり、字に於て絶と爲す、幼婦とは少女なり、字に於て妙と爲す、外孫とは女子なり、字に於て好と爲す。齏臼とは受辛なり、字に於て と爲す、所謂る絶妙好 と爲す、所謂る絶妙好 なりと。魏武も亦た之を記すること、修と同じ。乃ち嘆じて曰く、我が才の卿に及ばざるは、乃ち三十里なるを覺ゆと」。 なりと。魏武も亦た之を記すること、修と同じ。乃ち嘆じて曰く、我が才の卿に及ばざるは、乃ち三十里なるを覺ゆと」。 |
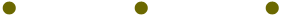 |
つまり蔡 は拆字の法を以て題したのである。この解にちとよけいな説明を加へておこう。女子の女はむすめ。齏はなます、また和え物。にらや、らつきやうや、にんにくなどの辛味のある菜をつきくだいて和え物にする。臼はそのための器であるから辛を受ける。説文に は拆字の法を以て題したのである。この解にちとよけいな説明を加へておこう。女子の女はむすめ。齏はなます、また和え物。にらや、らつきやうや、にんにくなどの辛味のある菜をつきくだいて和え物にする。臼はそのための器であるから辛を受ける。説文に は、受けざるなり、辛に从ひ、受に从ふ、辛を受くるは宜く之を は、受けざるなり、辛に从ひ、受に从ふ、辛を受くるは宜く之を すべし、といふ。籀文の すべし、といふ。籀文の は台に从ひ、 は台に从ひ、 に作る。辭は説文に、訟なり、 に作る。辭は説文に、訟なり、  は猶ほ辜を理むるがごときなり、といひ、籀文の辭は司に从ひ、 は猶ほ辜を理むるがごときなり、といひ、籀文の辭は司に从ひ、 に作る。今その一々については舉げないが、漢碑には に作る。今その一々については舉げないが、漢碑には を辭に通じて用ひた例はかなり多く見られる。ついでにいふと、今常用漢字として用ひられる辭の別體の辞は、 を辭に通じて用ひた例はかなり多く見られる。ついでにいふと、今常用漢字として用ひられる辭の別體の辞は、 の籀文の の籀文の の訛變した者である。つまり の訛變した者である。つまり の旁である台を行草書でつづけ書きした形が舌によく似た形になり、それを楷書にもどして辞の字ができた(圖參照)。それにしても今王羲之の書として傳はる曹娥碑の小楷があるが、あの文章、どふ見ても絶妙好辭とは思へないのだが。 の旁である台を行草書でつづけ書きした形が舌によく似た形になり、それを楷書にもどして辞の字ができた(圖參照)。それにしても今王羲之の書として傳はる曹娥碑の小楷があるが、あの文章、どふ見ても絶妙好辭とは思へないのだが。
魏武はいふまでもなく曹操。この話がもとになつて、有智無智、較ぶれば三十里といふことわざができた。智慧の有る者と無い者との差は三十里といふことである。
とまあおもしろいお話ではあるのだが、その實曹操も楊修もかつて江を渡り呉に至つたことはないのであるから、どふしてこのやうな話ができたのか、とんとわからない。 |

|
|
|







