場所は記憶する――私たちはいまどこに居て、どこへ往くのか
〈終章 場所と経験〉2
大江健三郎『燃えあがる緑の木』/多和田葉子『地球にち
りばめられて』
前田速夫
魂の日
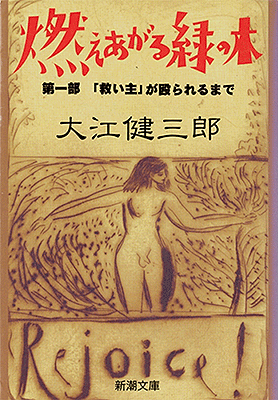

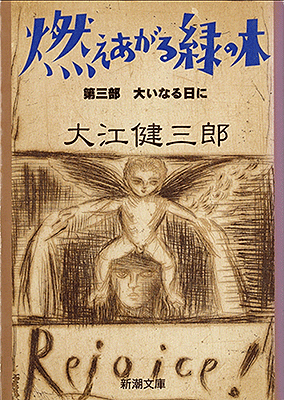
トポスの再生と言いましたが、それが現代で甚だ困難なのは、安部公房の『方舟さくら丸』などを例に述べました。けれども、右の三作は、新たにトポスを再発見して、作品に生命を吹き込んだ稀な例でした。
対して、作者が始めからその困難を承知しながらも、意図してそのトポスに執着し、なんとか未来を切り拓いていこうと奮闘していた作家もいて、それが大江健三郎です。私はその誠実で果敢な試みの例を、後期の『燃えあがる緑の木』三部作(新潮文庫、全三冊)に見ます。
原稿用紙二千枚に及ぶこの大作を、要約して伝えるのは到底不可能ですが、舞台となるのが、先に紹介した『万延元年のフットボール』『同時代ゲーム』と同じ、あの谷間の村であることだけは言っておかなくてはなりません。
これには先行作『懐かしい年への手紙』があって、
それを語るのは、今度はサッチャンという両性具有の人物。なぜこうした人物でなければならないのか、それには深いわけがあるのですが、それはこの小説をていねいに読めば分かることなので、ここでは省略します。
〈教会〉といっても、既成の宗教や新興宗教のそれではありません。そもそも神のいない現代、信仰対象となる人物のいない現代に、信仰の基盤のない場所で、どう「魂のこと」をすればいいのか、それが主題です。
「新しいギー兄さん」は谷間の指導者になり、魂の「救い主」に祭り上げられていくのですが、本人にその気はなく、その辺はきわめてあやふやです。
《自分たちの教会で、神があるかどうか、という方向づけの討論
なりなんなりをすることはなかったけれども、それだけに、わたし
は空屋という比喩が適当だと思うよ。なにもなかにはないかも知れ
ない。むしろなくていい。そうした繭のようなものが思い浮ぶか
ら、それに向けて、集中する。》
『月山』ではありませんが、またしても「繭」とあります。中空の空間が、ここでは空屋と呼ばれている。しかし、この新しいギー兄さんにとっては、神が存在しない、中身が空の空間に向って意識を集中する、それが「魂のこと」を意味したのでした。
結局、この新しいギー兄さんも、さきのギー兄さんと同じように、彼を快く思わぬ集団から襲撃されて死んでしまうのですが、私はそうした物語の展開とは別に、作中に縦横に引かれた古今の名言に立ち止まされました。
《(私の魂)といふことは言へない/しかも(私の魂)は記憶す
る(『伊東静雄詩集』)》
《もとより希望があるものか、/願ひの條があるものか/黙って
黙って堪忍して……/苦痛なんざあ覚悟の前(中原中也訳『ランボ
ウ詩集』)》
《親愛なる神よ、心からお祈りいたします、私が作品を秩序づけ
ることができますよう、お助けください、それが醜く、混沌とし
て、罪深いものであれ、あなたの眼に受けいれられる仕方におい
て、……乱れさわぎ、嵐をはらみ、雷鳴にみちているものであるに
はちがいありませんが、それをつうじて心を沸きたたせる「言葉」
が響き、人間への希望をつたえるはずです。それは平衡のとれた、
重おもしい、優しさと共感とユーモアにみちた作品でなければなり
ません……(マルカム・ラウリー『泉への森の道』)》
《両極の間に/道をさだめて人は走る/たいまつが、あるは燃え
る気が、/来て破壊する/昼と夜の/すべてこれらの二律背反を。
/肉体はそれを死と呼び、/魂は後悔と呼ぶ。/しかしもしこう呼
ぶことが正しいなら/喜びとはなになのか?》
《一本の木があって片側は燃えているが、片側は露に濡れた緑だ
/凝視する怒りと盲目の茂る葉との間にアッティスの像をかける者
は/自分の知っているところを知らぬかもしれないが、悲しみも知
らぬだろう。(イェーツ『揺れ動く』)》
《なんということがあろう?
声/それが表わす言葉はただひとつのみ、
『
《青年よ、祈りを忘れてはいけない。祈りをあげるたびに、それ
が誠実なものでさえあれば、新しい感情がひらめき、その感情には
これまで知らなかった新しい思想が含まれていて、それが新たにま
た激励してくれるだろう。(ドストエフスキー『カラマーゾフの
兄弟』)》
《人間存在の破壊されえないことの
)》
《ただひとつの今の中に、魂の日は生じる。(エックハルト)》
《不信仰の状態は、十字架の聖ヨハネが、夜と呼んだところのも
のとなる。信仰は言葉だけで、魂をつらぬかない。(シモーヌ・
ヴェイユ)》
《学ぶことについてのキリスト教的な考え方への鍵は、祈りが注
意力によってなりたつ、ということを認めることだ。(同)》
そして、この作品で大切なのは、ここで谷間の村の重要性、つまり「場所の力」を、 教会の礼拝堂を設計した荒先生という建築家に、K伯父さんの作品を引いて、このように説明させていることです。
《登場する人々は、この谷に生まれ育ち、一度は多様な世界であ
る谷間の外にでるが、やがてふたたび源としての谷に帰ってきま
す。谷間に流れる川は、本来の地形にあわせて流れると同時に、登
場人物たちの動きからすれば、逆に流れてもいます。仮想された地
形には逆勾配があるのです。「流出」の勾配と同時に、「帰還」の
勾配があります。
なぜ、逆の勾配が発生するのでしょうか。「四国の谷の森」に、
この谷に生まれた人々が死を迎えると、魂は森の樹木の根から空に
向かって昇っていくからです。森には、人を帰還させる力がある。
そのように「場所に力がある」のです。つまり、Kは、流出=生、
帰還=死という〈生と死と場〉の仮想された地形を構築していま
す。それが、Kが描出したひとつの「世界モデル」なのです。》
私が本書で一貫主張してきた場所の力、トポスの効用とは、まさしくこういうものなのでした。
それにしても、人は場所をめぐって、なんと豊かな経験をしてきたことでしょう。これを忘却し、空無化したことが、現代の不幸の始まりです。この場所の記憶を取り戻し、場所に力を与えていくことが、私たちにとっていかに大切か、よく分かってもらえたのではないでしょうか。
記憶と純粋持続

おしまいになりますが、以前に取り上げたことのある多和田葉子は、今後私たちが、私たちの文学が、トポスというものをめぐってどういうところへ行こうとしているか、新たな展望を与えてくれますので、近作の『地球にちりばめられて』(講談社文庫)に一言しておきましょう。
小説は、コペンハーゲン大学言語学科の院生クヌートが、たまたま自分が生まれ育った国がすでに存在しない人たちばかりを集めて話を聞くというテレビ番組を見るところから始まります。
《僕はなんだかいらだってきた。彼らはまるで、自分の国がなく
なったことを自慢しているように聞こえる。国がなくなったから、
自分たちは、特別な人間だと主張しているみたいだ。僕らだって昔
のデンマーク王国に暮らしているわけじゃないんだから、彼らとそ
れほど違わないんじゃないのか。祖先はグリーンランドを含む雄大
な王国で暮らしていたのに、僕はヨーロッパの端っこにある小さな
国の住人になってしまっている。》
あれこれ思っていると、急に全く違った種類の女性の顔が大写しになり、何か喋っている。彼女が生まれ育ったのは、中国大陸とポリネシアの間に浮かぶ列島らしい。一年の予定でヨーロッパに留学し、あと二ヵ月で帰国という時に、自分の国が消えてしまって、家に帰る事ができなくなってしまった。以来、家族にも友達にもあっていない。彼女が喋っているのは、手作り言語の〈パンスカ=汎スカンジナビア言語〉。デンマーク語とも、ノルウェー語とも、スェーデン語とも違うが、意味は通じる。
それがHirukoでした。クヌートはテレビ局を通して彼女と親しくなり、以後、二人はヨーロッパ中を移動して、アカッシュ、ノラ、ナヌーク、Susanooと知り合います。さまざまな言語が出入りしますが、民族や国家は関係ない。人が人と出会う土地と、コミュニケーションのできる言語さえあれば十分という見本のような楽しい小説で、アイデンティティとか、国民性とか、自分探しとかにこだわって、よけい世界を狭くしている現代人を嘲笑っているようなところさえある。
アルルに集結した六人のもとに、クヌートの母親が現われる最後の場面は、こう書かれています。
《「初めまして、アカッシュです」
と言ったが、おふくろはアカッシュの名前を手で振り払うような
動作をして、
「あんたは何なの?」
と訊いた。こんなひどい訊き方があるものか。ところがアカッ
シュはたじろがないで、こう答えた。
「クヌートの恋人です。あなたは?」
おふくろは絶句した。正直言うと僕も喉がつまって、君どういう
つもりなんだ、と普通ならばすぐに問いただすはずなのに、逃げる
ように席に戻ってアカッシュの様子をこっそり観察した。いつもと
変わるところはない。首をちょっとかしげて、おふくろの答えを
待っている。
おふくろが動揺してこの世で一番簡単な答えを返すことさえでき
ずにいるのを見ていると、気持ちに余裕が出てきた。
「この人は僕を産んだ。」
おふくろに代わって、僕が動詞を使って答えた。
「そして育てた」
と付け加えて、おふくろはHirukoを挑発的に睨んだ。
「あなたはクヌートのことをまだ何も理解していないのよ。」
Hirukoは風に吹かれるカーテンのように笑っていた。ちく
ちく皮肉を言われても、頭ごなしにどなられても平気なのだ。この
強さはパンスカを話しているところから来ているのではないか。パ
ンスカは僕らにもはっきり理解できる言語ではあるが、あくまで異
質さを保っている、Hirukoを北欧社会に溶け込ませて目立た
なくしてしまう言語ではない。しかもどんな言語とも直接はつな
がっていない。パンスカを話している限り、Hirukoはどこま
でも自由で、自分勝手でいられる。しかも会話が
ので孤独にならない。》
もちろん、これは極端な例です。はたしてこういったことが本当に可能なのかどうか、またそれ以前に自由でありさえすれば、もしくは自分勝手でいられさえすれば、それでいいのか大いに疑問なしとしませんが、ここまで覚悟しておけば、もう怖いことなんてないということでしょう。
ただし、作者はだからといって、無国籍でいい、コスモポリタンであればいい、無色透明な根無し草であればいい、と言っているわけではないので、そこは早合点しないでください。その証拠が、『古事記』に登場するヒルコ、スサノオを踏まえた、Hiruko、Susanooという命名です。前者は不具に生まれて蘆船に入れて流された神、後者はアマテラスの弟で荒ぶる神の代表格。ともに聖性を帯びた存在で、たとえ日本国が滅びても、その記憶が確かなら、私たちは空っぽにはならないのです。
記憶とは何度も言うように、場所の記憶であって、それはすなわち私たちの経験の総体です。意識の内面へと促された経験は、私たち個々人の恣意的で一回きりの体験とは違って、たとえ読書を介してであれ、私たちの身体と生活のなかで成熟します。生きられる時間とは、そうした作用を及ぼすもので、ベルクソンは、『物質と記憶』のなかで以下のように述べていました。
《観念が生きる力をもつためには、なんらかの面で現前する現実
にふれていなければならない。すなわち一歩一歩、それ自身を漸進
的に減少ないし、収縮させることによって、精神によって表象され
ると同時に、多かれ少なかれ身体によって演じられることができな
ければならない。われわれの身体は、一方ではそれが受け取る感
覚、他方ではそれが遂行しうる運動をそなえており、だからこそま
さにわれわれの精神を固定し、精神に底荷と平衡を与えるものであ
る。精神の活動は蓄積された記憶の集まりを無限にあふれ出るもの
であり、この記憶の集まりはそれ自身現在時の感覚と運動を無限に
あふれ出る。しかしこの感覚と運動が、生活への注意とでも呼びう
るものを条件づけている。こういうわけでちょうど頂点を下にして
立つピラミッドの場合のように、すべては精神の正常なはたらきに
おいて、感覚と運動が凝集することにかかっているのである。》
(市川浩訳)
文学は言葉から出来ていますが、言葉は元来、物質化した記憶です。ですから、個々の文学作品は、記憶と化した物資といえます。
記憶と並んで重要な経験については、森有正の言葉を引きましょう。
《頭で考えるのではなく、
い。(中略)感ぜられてくるということは、対象がそのあらゆる外
面的、したがって偶然的なものを剥奪され、内面に向って透明に
なってくることであり、それは対象が対象そのものに還ることだ、
と言い換えてもよいであろう。それを私は
言い表すことができない。そしてこれは
》(『遥かなノートル・ダム』)
ところが、いま私たちは、不感症を患って、対象とじっくり向き合う暇を与えられず、経験にまで高めることができないでいます。それどころか、肝心の記憶すら失って、一億総記憶喪失状態、一億総思考停止状態に陥っているのですから、ことは深刻です。だからこそ、たとえ文学作品という限られた場所であっても、それをじっくり読みこみ、感じることで、何がしか大切な経験をし、忘れかけていた記憶を取り戻すきっかけになればと、近現代の代表的な小説を取り上げて、その一つ一つが場所をどう扱っているかを検証してきたのでした。
本編のサブタイトルを、「私たちはいまどこに居て、どこへ往くのか」としたのも、同じことです。ずいぶん大げさなとわれながら呆れもしますけれど、この言葉は言うまでもなく、晩年のゴーギャンがタヒチ島で描いた大作「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」を踏まえています。これはキリスト教の教理問答に由来するようで、この作を手掛ける直前のゴーギャンは失意のどん底にあって、描き上げた直後に自殺未遂をしているくらいですから、ここから何か肯定的なメッセージを受け取ろうとするのは見当違いというものでしょう。
けれども、これが人類永遠の問いであるのは間違いなく、私は自分流に少し変型してみました。といって、もちろん筆者に明確な答えがあるわけではありません。「私はどこから来て」を抜かしたのは、私たちひとりひとりは、起源を知らずに生まれているからで、情けないことですが、正直に言えばむしろ、「我々は何ものでもなく、どこから来たのでも、どこへ往くでもなく、ただここにこうして居て」、その時が来れば死んで跡形もなくなるのが実情で、そのことさえふだんは何も考えずに暮らしているのがこの私であり、私たちなのでしょう。
反対に、今日の進んだ自然科学は、とうの昔に答えを出してしまっています。百三十七億年前、ビッグバンが生じた結果、宇宙が生まれました(それ以前は無といっていいでしょう)。やがて太陽系が形成され、地球が誕生したのが四十六億年前。そのうち海底で生命が発生して、それは単細胞生物から多細胞生物へ、植物から動物へと進化する。類人猿から別れて、アフリカで人類が誕生したのは七百万年前。原人、旧人、新人と進化して、十六万年前に現生人類ホモ・サピエンスが生まれる。こうなるまでの確率は、なんと一〇のマイナス一二三〇乗との試算があるそうです。
五、六万年前に各地に散らばり、日本列島にたどりついたのが、約三万八千年前。それが私たちの祖先ですから、「我々はどこから来たか」と言えば、直接にはアフリカの地から、もっとさかのぼれば宇宙誕生以前の無からやって来たという、ただそれだけのことになります。
そして、今日までどうにか生き延びてきたのは、交雑、つまり生殖の営みを絶やさなかったからでしょう。文明が発達しようがしまいが、それに恩恵を受けたり受けなかったりする人がいるだけの話で、そんなことは私たちが生きていることと何の関係もありません。
では、「どこへ往くのか」と言えば、熱核融合でエネルギーを放射し、年々明るくなっている太陽は、五億年後には爆発し、その結果地球も消えてなくなります。近年の急速な地球環境の悪化のせいで、おそらくそれよりずっと早く消滅するでしょう。それまでに太陽系以外の銀河宇宙への移住が実現していれば別ですが、人類が生存する絶対的な限界はそこまで。つまり、どこへも往くことが出来ずに滅亡します。
だったら、「私たちはいまどこに居て、どこへ往くのか」という問い自体、馬鹿らしいわけですが、にもかかわらず、ふだんは何も考えていないはずの私たちが、ふとそう問わずにいられないのはなぜでしょう。
それは、人が生まれて死ぬのが、自分の意志で選んだのではない、まったくの偶然でありながら、それ以外には選択の余地がない必然だからです。私たち人間は、偉人であれ凡人であれ、百パーセント等しく死ぬ運命にあります。どこへ往くかといえば、死の世界へ往く。それだけのことでしょう。
けれども、他人の死なら、そう突き放して言えても、個々人の死は別です。自らの意志で選び取る自殺を除くと、自分の死はいつまでも未知で未規定で、それを追い越すことができません。したがって、本当のところ誰一人として死後のことは考えられないのです。それは、誕生の起源を考えられないのと同じです。
最新の脳科学では、意識も記憶も、脳内現象に過ぎず、脳細胞中のニューロンが発火して、各シナプスが連絡することで生じるとされているようです。それなら、なおさら死後のことは何一つ考えられないのは当然で、信仰のある人もない人も、死ねば物質的にはゴミになり、無に帰するのは明々白々。
魂だって、同じことです。したがって、私たちがどうしてこの世に生まれてきて、こうして生きているのか、いくら考えても、答えが見つかるわけがありません。だからこそ、逆にいつまでも問わずにおれないのです。私たちは、いまどこに居て、どこへ往くのかと。そして、そのことこそ現に私たちが生きている証拠なのでしょう。
しかし、こう書きながら、はたして私は死の床にある身内に向って、あるいは死が間近に迫った自分自身に向かって「死は無だ」と言い切れるかどうか、自信がないのも事実です。「無」といっても、届かないだけで、だから語る方法がないのかもしれません。そこで、問いは再び元に戻ってしまいます。「私たちはいまどこに居て、どこへ往くのか」と。あるいは「私たちはどこから来て、どこへ往くのか」と。
- 著者略歴
- 前田速夫(まえだ・はやお)
一九四四年、福井県生まれ。東京大学文学部英米文学科卒業。一九六八年、新潮社入社。一九九五年から二〇〇三年まで文芸誌「新潮」の編集長を務める。一九八七年に白山信仰などの研究を目的に「白山の会」を結成。著書に『異界歴程』『余多歩き 菊池山哉の人と学問』(読売文学賞受賞)、『白の民俗学へ 白山信仰の謎を追って』『古典遊歴 見失われた異空間 を尋ねて』『「新しき村」の百年 〈愚者の園〉の真実』『海人族の古代史』『谷川健一と谷川雁 精神の空洞化に抗して』『老年の読書』など。
本連載と同時進行で「三田文学」に『対比列伝 作家の仕事場』を連載中。