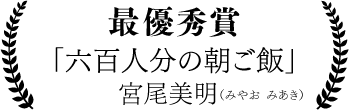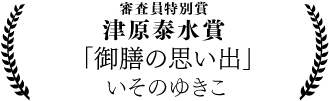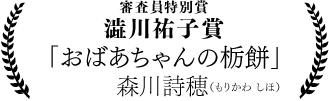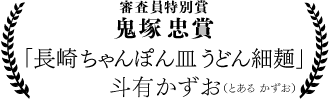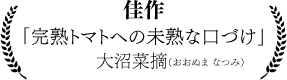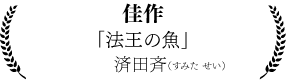人はおらん、飯はなし、魚はいかん、菓子はくえ――。どこかの地方の貧しさを嘆いた俗謡か、あるいは金田一耕助ものの猟奇殺人の符丁かという響きだが、日本人用のインドネシア語・マレー語独習書なら大概は、前書きの部分か埋め草の囲みの一つにこのフレーズが載っている。オランウータン、ナシゴレンと書けば、ああそうかと思い当たるだろう。あちらの言語では通常、名刺を後ろから形容されるので、それぞれ元々は、森の人、焼き飯、の意である。一万を超える島々が連なるその地域の東の方に、イカンパウス、法王の魚を捕る村があった。鯨である。そこを訪れた時の話だ。
その頃あった七、八隻はどれも、漕ぎ手十人程度の小さな木造船だった。沖に出るに従ってじわじわと船の底に溜まる海水をかき出す役も、舳先に立って銛を投じる男も含め、一つの船が一つのチームをなす。船の数と同じだけしかいない銛投げ男は村の名士である。身長の倍ほどもある銛を投げて抹香鯨を仕留める姿に憧れ、村の男児は物心つくと、岩場から海中の的に棒を投げ付ける遊びに興じる。村の男児はみな、まず銛投げ男になる夢を抱く。
「銛投げ男」と呼んでしまうと実体とやや異なる。獲物に近づけた船から銛を投げるのでなく、銛を持ったまま、体当たりをするように海中に没するからだ。ぞの海域では南極大陸から北上する海流が強く、南洋とはいえ水温は低い。銛が外れて船にはい上がり、服を着たままびしょびしょに濡れそぼって膝を抱え、がたがたとしばらく震えている。その姿がまた絵になる。
村の漁では最大の獲物はなんと言っても抹香鯨であり、他に鮫、海豚、エイの類いを捕っていた。大きなものばかりなのは銛で突くのだから当然で、にもかかわらず他の漁法は一切見なかった。不思議なことに釣り針も釣り竿も漁網も存在しない。訳は誰に聞いても要領を得ない。網がどんなものか、何に使うのかはみな知識としてはあるのだが、ああ村にはないよ、というばかりだった。
陸を見ると、田も畑もない。主食の米や干し玉蜀黍は、山の向こうの村から物々交換で手に入れるのだという。それを購う村の産品は干した鯨肉と塩であった。
鯨肉は羊羹大に切り、浜辺に吊す。陽光に炙られてしたたり落ちた脂は燃料に、からからに乾いた身は保存食であり、貨幣の代わりであった。
お金だから、そうそう食卓に上るものでもない。海豚の串焼きなどは大御馳走の部類で、ぼそぼそした飯にぼそぼそしたエイ肉かぐにゃぐにゃした鮫肉があるばかり。それでも飽かず悔い続けたのは、サンバルという唐辛子ベースの調味料が絶品であったゆえだ。
サンバルとは何もその村だけのものではない。その辺りの国々の全域で食卓になくてはならぬものだ。だが、中身は地域によって相当に異なる。大まかにいえば唐辛子、大蒜に、銀杏大の赤玉ねぎ、香草などを石臼でつぶして煮詰め、味をつけたものだが、あるところでは甘辛い緑色のペーストであり、隣の地域では真っ赤でややほろほろした味噌のようなものであり、別の島では一切火を通さず、ココナツオイルの風味を効かせた辛いサラダ様の付け合わせみたいなものもある。
その村のサンバルは、それまで食したどれとも違った。大した漁がなく、主菜がサンバルのような食生活が続くと、いやでも意地汚い舌が、これはコブミカンの葉の風味だな、と少しずつ原材料を探り当てていく。だが、どうにも不思議なのは、発酵食品の旨みだった。要は塩辛の味がするのだ。烏賊でもない、鰹の内臓を使った酒盗でもない。第一、そんなもの銛で突けやしない。
懇意の女に聞くと、クリルを塩に漬け込んだものだ、と教えてくれた。オキアミ? そうだ、キムチにも入れる、アミの塩辛の味だ。だが、鰯を獲る網すらない村でどうやってアミを捕るのか。
見せてやろう、と女が笑った。手を引かれ、暗い台所に入ると、大きなエイが床に転がしてある。女は、その日に浜で上がったばかりのエイを持ち上げ、小さなナイフですっと腹を割いた。
手には小さな塊が握られていた。わかるだろう、胃袋だ。ぷるぷると動いて見えた。ほら、中はクリルではち切れそうだ――。女の笑い声がした。
村を去る日、ある長老からこんな話を聞いた。かつて、漁網とエンジン付きの大型船を提供するのと引き替えに、一切の鯨漁を止めるように要求する外国人の男たちが来たことがあった。だが、幾度出してもその船では満足な漁がなかった。沖へ沖へと漁場を求めた末、ある夏の日の出港を最後についには帰らなかったという。
「食の思ひ出 コンテスト」
佳作
法王の魚
済田斉(50歳・男性)