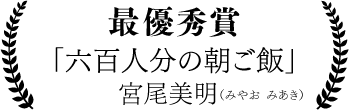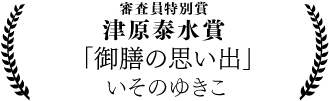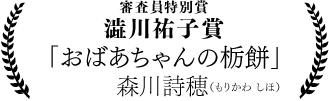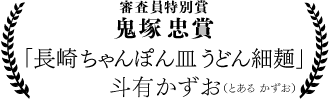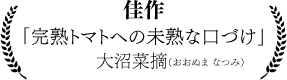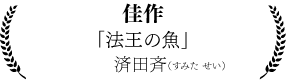母の田舎の山には、大きな栃の木があった。毎年春になると、薄紅色の小さな花が咲く。稲穂が実る頃には、茶色い実が鈴なりになって塾したものから落ちてくる。厚い果皮を剥くと、中からは艶々と照った褐色の実が顔を出した。我が家では、毎年秋になるとその実を拾う手伝いに行くのが恒例行事になっていた。
栃は灰汁の強い植物だ。そのまま食べると非常に苦く、舌にピリピリとした痛みが走っていつまでも消えない。ただ、この灰汁抜きには大変な手間と時間がかかる。約一カ月の天日干しの後、一週間ほど水に浸して灰汁を出す。包丁でひとつひとつ丁寧に鬼皮(外側の硬い皮)を剥き、火にかけて二時間ほど煮たら木炭を入れ二昼夜寝かせる。粘土状になった灰をきれいに洗い落とすと、中から黄金色に変わった実が現れる。最後に、薄皮を丁寧に剥いで、ようやく食べられる状態になるのだ。祖母は毎年、実を収穫してから二カ月以上かけて、たった一人でこの作業をこなしていた。
十二月の最後の土日には、毎年決まって祖母の家で餅つきをすることになっていた。お正月用の白餅と一緒に、秋に採った栃を使って栃餅をつくのだが、私は祖母の作る栃餅が大好きだった。もち米と一緒に栃の実を蒸すと、家中に香ばしい薫りが広がった。蒸し上がると臼に移してつくのだが、杵を下ろすたび、ほくほくした栃の実がつぶれ、真っ白だったもち米が、だんだん茶色に色付いていく。祖母はその栃餅に、ふっくらと煮た大納言の餡をまぶして、三時におやつに出してくれた。早朝からの餅つき作業にほど良く疲れた体には、あの小豆の甘さから見え隠れするほろ苦さがたまらなかった。
祖母に病気が見つかったのは、私が高校一年生の時だった。ちょうど、その年に収穫した栃の実の灰汁抜きに取り掛かる季節だ。大腸にできた癌は、その周りの臓器や骨にまで転移していた。子どもだった私には医学的な説明は分からなかったが、レントゲン写真からは、左の腰骨が半分溶けてなくなっているように見えた。病気の進行度から手術はできず、高齢のため放射線治療も行わないことを決めた。祖母には病名を告げないことを家族で申し合わせ、残された日々を穏やかで心安らぐ時間にする道を選んだ。
学校帰りに祖母が入院する病院に顔を出すこともあれば、週末には家族で祖母を囲み、日々の出来事や思い出話に花を咲かせた。年の瀬が迫ったある日、
「冷凍庫に、今年採った栃が入れてあるけぇ。味は多少落ちるだるおけど、ないよりはましだろうと思ってなぁ。」
祖母はさらりとそう言ったが、私たちは驚いた。
栃の実は、灰汁抜きした状態では長期保存ができない。本来は、天日干しで乾燥させた状態で保存し、食べるときに合わせて灰汁抜きをするのだ。祖母もまた、毎年年末の餅つきに合わせて灰汁抜き作業をしていた。それが今年は、早々に灰汁抜きを済ませ、その実を冷凍庫で保存していたというのだ。まるで、自分の体がこうなることを予見していたように。それに加えて、栃の灰汁抜きは大変な労力を必要とする。医師の話では、入院前から相当な痛みを感じていたはずだ。あの体で一人台所に立ち、栃の実を一つ一つ剥く祖母の姿を想像すると胸が痛んだ。
それでも、祖母の思いを無駄にしないために、例年通り餅つきを行った。祖母のいない餅つきは監督不在のベンチのようだった。母が小豆を煮て栃餅も作ったが、家族全員がおばあちゃんの作った方がおいしいと言った。自分の栃餅を酷評された母は、「年の功には勝てないよ。」と嬉しそうに泣いた。
祖母が亡くなったのは、病室で家族揃ってお正月を迎えた十日後のことだった。もう食事が喉を通らなくなっていた祖母だったが、母が作った栃餅を「おいしい。」と頬張った時のままの笑顔だった。
あれから十五年。私は結婚を機に実家を出て、二児の母になった。母も、三人の孫をもつおばあちゃんだ。恒例だった栃の実拾いはなくなり、お正月用の餅つきも実家で電動の餅つき機を使うようになっていた。祖母が亡くなって数年は秋になると栃の実を拾い、母が灰汁抜きに挑戦していたが、一度もうまくいかなかった。栃の実の灰汁抜きは、実の乾燥具合や使用する水の温度、煮る時の沸騰時間など、細かい一つ一つの作業が仕上がりに影響するそうだ。全ては祖母の頭の中にしかなく、そのレシピを持ったまま祖母は天国へ行ってしまった。「おばあちゃんの栃餅」は、私たち家族にとって幻の味になってしまったのだ。
そして昨年の夏、あの栃の木があった山も、とうとう人手に渡ることが決まった。もう何年も行っていなかったが、祖母との思い出が詰まった山が、他人の物になるのは少し寂しかった。
そんな時、母が最後にもう一度栃餅作りに挑戦したいと言い出した。稲刈りの季節になり、十数年ぶりに栃の実拾いに出掛けた。子どもたちは、「山」という非日常的な空間に始めは大はしゃぎで走り回っていたが、そのうち誰が一番多く拾えるか競争が始まった。母は、まるで幼い頃の私たちを見ているようだと、懐かしさに目を細めた。
栃の実拾いの帰り、せっかくだからと杵と臼を使って餅をつこうということになり、祖母が亡くなって以来空き家になっていた家に立ち寄った。もう十年以上使っておらず、誰も手入れしていない杵と臼が果たして使えるのかどうか期待半分だった。しかし、最後に使ったとき丁寧に手入れをして仕舞っていた祖母の仕事の賜物だろうか、それは十五年前のあの時のまま、納戸の一番奥に布を被って鎮座していた。
母と二人、臼を運び出しながら傍らの本棚にふと目をやった。そこには、古い雑誌やアルバムに交じって、同じ背表紙の大学ノートが何十冊も並んでいた。その中の一冊を手に取ると、ノートというより帳面といった方が相応しいその表紙には、「献立帳№9」と書いてあった。
祖母は六十歳で定年を迎えるまで、ずっと警察学校で調理員の仕事をしていた。栄養士という資格が一般的ではなかった時代である。専門的な資格や知識こそなかったが、学生たちのために栄養バランスに配慮した、美味しくてボリュームのある献立を考えるのも祖母の仕事だった。そのノートには、日々の献立の記録とレシピが丁寧な字で綴られていた。そして、小さい頃祖母に作ってもらった記憶のある料理もたくさん並んでいた。
気づけば母と二人、懐かしさに耽りながらノートの頁を次々とめくっていた。そして、胸に一つの小さな期待がよぎった。私は、黙って頁をめくり続けた。口に出して、もし見つからなかった時に母を落胆させたくはなかった。次第に胸が高鳴り、ノートをめくるスピードが早くなっていくのを感じた。何冊目かのノートに差し掛かった時、その文字は、確かに私の目に飛び込んできた……「栃餅」。隣には、栃の実の灰汁抜きの仕方が丁寧に記されていた。
祖母がこのノートを誰かに見せるために書いていたとは思えない。しかし、少なくともこの頁だけは、誰かに見つけてもらうのをずっと待っていたような気がした。
祖母がそうしていたように、母は年末の餅つきに合わせて栃の灰汁抜きを始めた。手伝いを申し出たが、丁寧に断られた。最後まで一人でやり遂げたい気持ちはよく理解できたので、静かに見守ることにした。
十二月の最後の週末、四人の兄弟と三人の孫たちが実家に集った。玄関を開けると同時に、もち米を蒸す香りが漂ってきた。弟たちが代わる代わる杵を持ち、玄関先で威勢のいい声を上げていた。私は、窓越しにその姿を眺めながら、子どもたちと一緒に餅を丸めていった。近頃では珍しい光景なのだろう、近所の家から出てきて顔を覗かせる人もいた。
昼食を挟んで、いよいよ栃の実を蒸すあの香ばしい匂いが家中の空気を包んだ。頬のあたりが紅潮するのを感じたが、決して蒸し器から上がる蒸気のせいばかりではないことは確かだった。蒸し上がった栃の実は、十五年前の記憶のまま黄金色に輝き、ふっくらと実をほどいていた。
弟が杵を振り下ろすたび、もち米は粘り気を増し、栃の実を包み込みながら優しい茶色に色付いていく。その光景のすべてが、幼い頃の懐かしい思い出を呼び起こしていった。
三時にはまだ少し早かったが、母は一臼目についた栃入りの餅をおやつのために半分取り分けた。いったい何時に起きて仕込んだのだろうか、自家製の餡を絡め、祖母がそうしていたように、大皿に盛って出してくれた。こし餡は、栃の実の灰汁抜きと同じくらい手間と経験を要する。母の作ったこし餡は、みずみずしく輝き、栃餅に華やかな化粧を施していた。
「いただきます。」
気づくと、子どもたちよりも先に頬張っていた。こし餡のしっとりとしてなめらかな食感が広がり、その後で、もっちりした栃餅の絶妙なほろ苦さが見え隠れした。人は、十五年以上経っても、味の記憶を失わないのだと、この時初めて知った。母の作った栃餅はまさに「おばあちゃんの栃餅」だった。
その時、四歳になる長男が口の周りに餡子をいっぱいつけながら言った。
「おばあちゃんの作った栃餅おいしい。」
従兄も続いた。
「おばあちゃんの栃餅最高!」
私にとっての「おばあちゃんの味」は、祖母から母へと受け継がれ、我が子にとってもまた、「おばあちゃんの味」になったのだ。
あの時、祖母が遺した幻のレシピを見つけたことは、決して偶然ではないような気がした。いつの日か、私も母からこの味を受け継ぐ日が来るのではないか。そして、「おばあちゃんの栃餅」として娘に伝える日が来るのではないか。そうしなければならない。いや、そうしたいという思いが、湧き上がってくるのを感じた。栃の実拾いこそできなくなってしまったが、この味だけは我が家から絶やしてはいけないと思った。
ただそれは、もう少し先のお話。なぜなら、「おばあちゃんの栃餅」を引き継ぐ日が遠ければ遠いほど、私にとってはきっと幸せだからだ。
「食の思ひ出 コンテスト」
澁川祐子賞
おばあちゃんの栃餅
森川詩穂(31歳・女性)