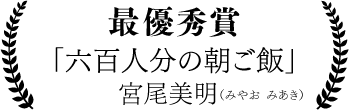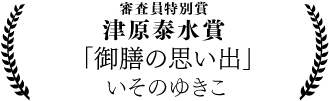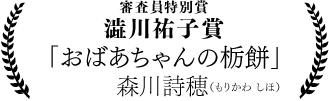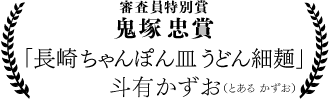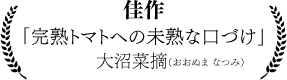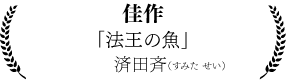忘れられない食の思い出は数限りなくあるが、一番忘れられないのは、なんと言っても富士山頂八合五勺の山小屋での朝ご飯である。朝ご飯と言うが、実際は未明のご飯といった方がいい。ご来光を見るために山小屋を出発するのは二時間以上前に小屋を出なければいけないから、食事はその前になる。半分体が寝たままで掻き込んでいるご飯がどんな味だったのかは想像しかできないが、食事の後の粗末な長い板のテーブルの上にはどんぶりはひっくり返っているものが多くあったが、不思議とみんな空だった。大小のどんぶりを片付けながら、何だかホッとして自然に笑みが浮かんできた。
当時十八歳だった私は、ひょんな事から故郷から離れたこの富士山の山小屋でバイトをしていた。山に登ることもバイトも初めてのことだった。若いと言うことは全身が好奇心の塊で、全く怖いもの知らずだった。真夏の富士といえども朝夜は氷点下十度以下になるし、昔のことで水は富士山には雪の溶け水(真夏であっても根雪は深く、そこに筒を突っ込んでぽつりぽつりしたたり落ちる溶け水が生活用水のすべてであった)しかなかった。寒いことも水が蛇口から出ないことも、何も知らなかった。その上、バイトの一番主要な仕事の朝の食事の準備をする料理の事も、何一つ知らずに富士にいた。
「起きて飯作れ」
山小屋に着いた次の朝、たたき起こされて、調理場のような場所に放り込まれた。六百人分の食事を作るよう言われていたが、家族のご飯すら作ったことがないのに、六百人分のご飯など想像できなかった。それより何より寒かった。
「氷点下十八度か」
小屋を取り仕切っていた若者は、独り言をつぶやくと、そのまま外に出ていった。たたき起こされたのは、私ともう一人の若い女性。昼間来ているおばさんたちは夜には山小屋にいなかったから、若い女は、小屋では二人きりだった。
カランコロンカランコロン――鉄板の上を下駄で歩いたらこんな音がしたかもしれないような、富士山の直接地肌を感じる土間に入ると、まさに冷凍庫の中だった。息はそのまま固まり鼻水も同じだった。
「寒いな」
声がそのまま凍りそうで、二人で目配せをしながら前日教わったように人間が何人も入りそうなお米の入った巨大な鉄の釜をおくどさん(かまど)に二人がかりで乗せる。これが二つある。それとこちらも見たことがない巨大な鍋。なみなみと水が入っている。一日筒からしたたり落ちた雪の溶け水全部が入っているような量だった。
「米みたいなもの綺麗に洗わんでもいい。水がもったいない。すぐに火に掛けりゃあいい」
手がちぎれるような雪の溶け水に実際手を入れて洗った記憶がなく、もう火をつけるばかりなっていたような気がする。昼間おばさんたちがやっておいてくれたのかもしれない。さあいよいよ火をつけるのである。これがまた難しい。酸素が薄く火などなかなかつかない。新聞紙と灯油と薪。山のように並べてあるそれらをひょいひょいと取り寄せながら、山小屋を取り仕切っていた若者が見本を見せてくれたようにうまくは行かない。
ふたが開いたままの灯油の缶の中に新聞紙を丸めて入れて、かまどの中に放り込みマッチで火をつける。勢いよく点いてもすぐに元気がなくなる。薪を入れると知らぬ間に消えてしまう。全く火を燃やし続けることがこんなにも難しいとは知らなかった。灯油を新聞紙にも薪にもつけ放題つけて、何とか釜から湯気が上がったときの感動は忘れられない。ぐつぐつという音、黙々と上がる湯気、土間一杯に広がるご飯が炊ける何とも言えない香り。その頃になると隣のお鍋もお湯もぐつぐつ。もう寒さなどどこかに行ってしまって南国のような汗まみれになっていた。ご飯の匂いがあんなにも濃く甘いものとは知らなかった。ぐつぐつとまるでメロディのような釜のふたの上下運動、見ているだけで幸せになった。
しかしのんびりとはしていられなかった。ぐつぐつと煮えたぎるお湯の中に、長い棒のような麩を細く薄く山のように切った。お湯の中には昆布も煮干しもだしなど何もない。ただ味噌だけを延々とたらし込むのである。量の程度など分かるはずもなかった。ただ置いてある分全部を入れたら、それでいいはずだった。ご飯も炊けて盛りつけが始まった。山のようなどんぶりが運ばれてきた。山小屋の全従業員で、六百人分の食事の準備だった。炊きたてのご飯の味は、この世にこんな味のあるご飯があったんだと感動の極みの味だった。甘くて優しくて自然の味。ご飯におかずなど要らない味。それがご飯だと実感した。それでも味噌汁と佃煮をつけて一人分。味噌汁はただ麩だけが入ったまさに味噌だけの汁。なのに、ふわふわと浮いた麩を潜らすとさっと味噌を吸い込んだ不思議な模様と味。佃煮は昆布か、味付けじゃこだった。それすらも真っ白い(そんなに綺麗に洗ってないにもかかわらず)ご飯に良く似合って美味しかった。誰も残さなかったのが、その証拠だった。
一度に食事の場所には入れるわけもなかったので、食べ終わった人たちから順次ご来光に出発し、次のグループが食事という具合に長い長い時間の食事時間だった。その間、まるで戦争状態。寒いのか暑いのか、ごった返す中で頭は全く空っぽだった。それにしても食事の匂いというものはなんと人の心を温かく幸せにするものかということを知った。延々と続く食事の間中漂っていたご飯の匂い、味噌汁の匂い、佃煮の匂い何もかもごっちゃになった食べるときの匂い。私は生きる匂いだと実感した。残り物のご飯をほおばりながら、ご飯の甘さとちょっぴり感じるしょっぱさ、大地の匂いまで味わう気持ちだった。
生涯でおそらく六百人分の食事をうら若い二人の女性で作ったという経験などこのとき以外はないだろうと思う。家族わずかな人数の食事を作るのでさえ面倒だなと思うときもある。そんなとき、あの時のことを思い出すと自然に笑えてくる。お客さんの残した(出した分はいつも殆ど完食してくれていたので)巨大な釜の底にこびりついたお焦げを二人できゃっ!きゃっ! 笑いながら取り出して、なぜかお塩もなかったので、これまた残った佃煮でおにぎりを作り、富士の岩肌に腰を下ろした。はるか下界に目をこらすと、まるで小さな蟻のように行列を作って上ってくる人の姿がくっきりと見えた。
手を伸ばすとつかめそうな空がすぐそばにあった。気持ちよかった。一口一口お焦げご飯の香りを吸い込みながら、ほおばったおにぎりの味は最高だった。
「いつまで遊んでいるんだ」
山小屋の若者に促されるまでもなかった。次の仕事は、六百人分のお客さんのごろ寝をした布団干しの仕事が待っていた。
「おにぎり食べるまで待っていて」
「俺も食う」
やってきた若者の手には三倍ほど大きなおにぎりが握られていた。
「いつの間に?」
こびりついた最後のおにぎりは全部私たちが作ったはずではないか。なのに、あの巨大なおにぎりはどこから?
「残り物だよ」
「残り物は全部私たちが握ったよ」
「本当の残り物だよ」
意味が分からなかった。お客さんは全部食べきって山に行く、今まで残したのは見たことがない。お釜に残ったご飯は私たちがおにぎりにする。
「どこに残り物があったの?」
「そりゃあ、あるさ。お客さんの残り物だよ」
「えっ!いつも空っぽじゃなかったの?」
「そんなわけないだろう。お客さんがみんな食欲旺盛だとは限らないさ。どんぶりを片づける前に、残ったご飯はみんな一つにまとめておいたのさ」
「それでいつもきれいだったの?」
「そういうこと」
「残り物って嫌じゃない?」
聞きたくても聞けないことを、もう一人の彼女が聞いた。私が聞いたら嫌みになる言葉も彼女が聞けばやんわりと優しく包み込むようだった。
「俺さあ、残ったご飯が可愛いのよ。愛おしいのよ。ここじゃ食べ物はこの上なく貴重品だろう。何でも地上の十倍の値段はかかってる。高いお米代、それより高い運賃(馬か荷背負の人足)を使って、何より貴重な水で、綺麗な姉ちゃんの手でたかれてうまくできあがったご飯を残すなんて考えられないよ。みんなには一晩のご縁、山を下りりゃあ、別の世界の住人。俺には山開きの間中、山小屋が俺自身。山小屋にあるもの全部が可愛いのよ。分かるだろう。ここは富士山だよ。残り物を捨てる場所なんてどこにもないさ。まして、こんなうまいご飯を。うまいぞ。最高だよ。さあ、食ったら布団干しだ。今日はいい天気だ。今日は良くてもいやいや今は良くてもすぐに天気は変わる。絶好の今だから頑張って布団干そうぜ」
最後の一口をほおばって飲み込んで若者は立ち上がった。見上げる私の目に、雄大な富士の雄姿と若者が重なり合って神々しく見えた。
「食の思ひ出 コンテスト」
最優秀賞
六百人分の朝ご飯
宮尾美明(70歳・女性)