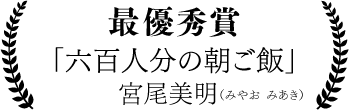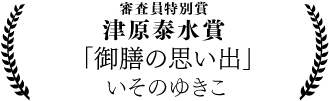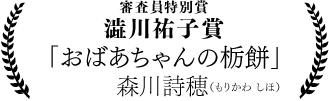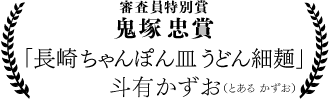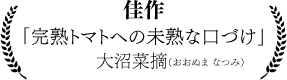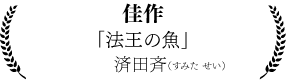太陽の光が葉についた露の表面を撫で上げ、起きて間もない子どもの眼差しのような、曖昧で綺麗な色をした空へと吸い込まれていく。自らの重さか、はたまた朝日の眩しさに耐えきれぬのか、露はそれ自身の形を壊してしまう。軽くなった葉は湿った緑色をして、そしてなお、小さな水滴を乗せたままである。
私たち姉弟の一日は、朝露がまだ残る時間から始まった。祖父の運転する軽トラックの荷台に乗り込み、砂利道を進む。青い稲穂から立ち上る、ほんのりと甘い匂いが寝ぼけた脳へと朝であることを伝える。右手に田んぼを見ながら真っ直ぐ歩くと、祖父は左側のハウスへと入っていく。十年前、まだ七歳だった弟の手を引きながら、私は祖父の背中を追いかけ重い扉を開けた。
ハウスの中は、身体中の血液に溶け込むような濃厚な土の匂いでいっぱいだ。真ん中には人一人が通れるくらいの土の通路ができ、歩くと長靴に乾いた土の断片がつく。両側の視界は背の高いトマトの茎で遮られ、背景の濁った白いビニールが植物の青さをより一層引き立たせている。脳みそは既に野菜の茎や実から出るのであろう、そこに命が存在しているのだという生々しい、青々しい匂いと、それらを支える土の湿り気のある凝縮された匂いに侵されている。ここを出たくないという感覚に囚われ、生命のあるものから出る匂いは、愛おしく中毒性のある麻薬のような成分で出来ているのではないか、と思うほど私の身体へと入ってくる。
祖父は一通り野菜の成長を確認したようだ。弟と私は、入り口に佇んだままその姿を見つめていた。すると、祖父が手招きをした。私たちは荷台から運び出した籠を背負い、トマトを手で触りながらしゃがんでいる祖父の元へと駆け寄った。
トマトは立派だった。大きくて赤くて、青い部分が少し残っていた。しっかりと茎に支えられ、その強そうな茎でさえたわむような重みを有していた。祖父が鋏を取りだしてヘタの近くを切る。ぷちん、という音がやけに大きく聞こえた。それはこのトマトを自由に食してよいという合図のようだったが、今は栄養をもらって大きくなったトマトが成長の終わりを、トマトとしての人生の終わりを告げられる音であったと考えている。
祖父はそのトマトを背中の籠に放り込む。私たちは祖父の真似をして、同じような作業を繰り返す。ハウス内の野菜を全て収穫するわけではない。食べ頃になっているものを見極め、採っていくのだ。まだ成熟していない野菜を収穫してしまい、叱られることもしばしばあった。どのぐらいの時間、そうしていただろうか。長靴と、履いているズボンに土の匂いが移り外へ出てみると、空は均一な青色になっていた。祖父が軽トラックのエンジンをかける。私は弟と一緒に、荷台に籠を置く。が、そこから一つのトマトを取りだし掌にしっかりと握る。私たちはハウス横にある井戸へと向かった。それは地下から水をくみ上げて、鉄の筒から冷たい水を出してくれる。掌にのせたトマトは、ひび割れた道路のアスファルトとは対照的な生命力を澄んだ空気の中で放っていた。精一杯膨らんだ実。ただ大きくなるだけではなく、中身をしっかりと詰めて成長したのだろう。一度傷つけてしまうと、内側から溢れだしてしまうような繊細さも併せ持つように見えた。
井戸の取っ手を力強く動かすと、三回ほどの上下運動で水が勢いよく飛び出してきた。その下にトマトを差し出し、形を確かめるようにじっくりと指でヘタや実をなぞる。弟とお互いのトマトを洗い終わると、私たちは口を大きく開いた。出来る限り大きく開き、実にかぶりつく。内側のぐじゅぐじゅとした部分にはまだ辿りつかない。子どもだから口が小さいし、なぜか外側の皮に沿って噛み切ってしまうからだ。この赤い部分はトマトが纏うドレスだ。あっさりとして、しかし厚さがある。くし切りにすると皿の方へ隠れてしまうが、内側を守るために必要な部分。手でトマトの感触を確かめられるのはこれがあるからに違いない。
口の中に残った皮を飲み込み、二口目へ移行する。最初とは異なり、控えめな口の形で実に口づけをする。歯の先で薄い膜のようになった赤い部分を引き裂くと中身が姿を現した。トマトの特徴ともいえる、ぐじゅぐじゅで濃い部分である。唇をすぼめ、少しずつ吸い出すと口の中に中身が入ってきて、そのまま丸ごと一つをかじってしまいたい衝動を掻き立てる。この溶けるようで掴めきれない、甘く酸味を含んでいる味わいは、幼い私に人生で初めての官能的な刺激を与えた。本来見ることのないその部分は、隠れ隠されて熟したのだろう。根が吸い上げた栄養分と水分を、茎を介して受け取り蓄える。その実を今食している自分。一体化しているのだ、と思った。実に含まれた全ての物を自分の体へと取り込んでいるのだ。それは必要であり、しかし不思議であり官能的な感覚すら覚える行為なのだ。
まだトマトの半分しか食べていないのに、祖父の声が聞こえた。タイヤに足をかけ、荷台へよじ登る。横倒しになった籠から、車が大きな砂利を踏み上下する度にトマトが転がる。それが面白くてずっと見ていた。
東京の生活で野菜にかぶりついたことはない。洗って切って、調味料をかけて食べる。ただそれだけだ。祖父母の住む田舎に行けば、また出来るだろうか。自分も野菜も生きている。そう、あの時私は確かに生命のあるものを口にしたのだ。すっかり失くしたと思っていた、勢いよく生きる力が右手から溢れ出てくるような、そんな気がしたのだった。
「食の思ひ出 コンテスト」
佳作
完熟トマトへの未熟な口づけ
大沼菜摘(19歳・女性)