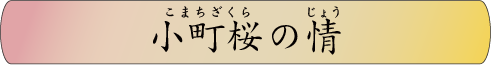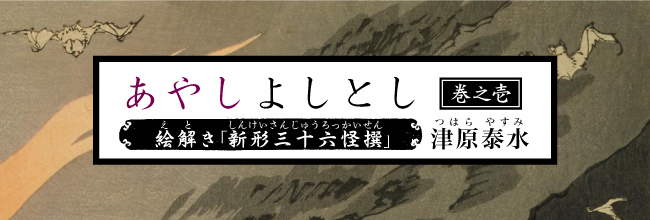タイトルに小町桜【こまちざくら】とあるから、常磐津節をバックに舞い演じられる『積恋雪関扉【つもるこいゆきのせきのと】』の一齣に違いないのだが、なぜか小町桜の「情」となっている。役名は小町桜の「精」である。芳年が勘違いしていたのか洒落たのか、その辺の事情はさっぱりと分からない。画集では「精」、国立国会図書館では「情」として整理されている。ここでは読めるがままに「情」とする。
幽霊のようだがあくまで桜の大樹の精であり、小町と名付けられていながら小野小町とは無関係。でも本質は小野小町であるという、メタ物語とも楽屋落ちともとれる構造がこの舞台を支えている。SF作家で云えば田中某が書きそうな、どこまで本気なんだかよく分からない話だ。架空の例えで恐縮だが、映画で云えば『ゴジラ対ガメラ』が実現して、そこにキングコングも絡んでいるといった風情。知名度重視で例示したので怪獣どもになってしまったが、徳川時代、六歌仙はそのくらいポピュラーなキャラクターだった。
筋書を記す。逢坂関【おうさかのせき】は名の知れた桜の大樹の程近くに、良岑宗貞【よしみねのむねさだ】という男が籠もっている。これは僧正遍照【へんじょう】の俗名であり、はや六歌仙の一人が出てきた。楽しみにしていた桜の開花を待つことなく崩御した、仁明【にんみょう】天皇の菩提を弔っていたとされる。嘉祥【かしょう】三(八五〇)年くらいの話だというのがここに分かる。
偶然にもその関を訪れたのが、宗貞がむかし交際していた小野小町姫――問答無用でこのネーミングだ。そういえば昔、若き日のアインシュタイン博士がマリー・キュリーと恋におちる『ヤング・アインシュタイン』という映画があったが、そんな感じである。
「まあまあ、せっかく再会したのだし」と両者の仲を取り持とうとするのは、関守役人のその名も関兵衛。ところがこの男、なんだか怪しい。怪しんでくれと云わんばかりの言動を重ねる。そのうえ落した割符【わりふ】を宗貞に見られ、これが怪しい男だという決定的な証拠となる。具体的にはどういう証拠なんだ、などと野暮を云ってはいけない。割符といえば証拠なのだ。ヒチコック映画のマクガフィンみたいなものだ。まさか謀叛の企てでも? と察した宗貞、事態を帝に伝えるべく小町姫を京へと向かわせる。
じじつ関兵衛は天下取りを目論んでいた。だから具体的にどうやって? と野暮を重ねてはいけない。なんとなく出来ちゃうような気がしていたのだ。夜桜の下で酒を飲み飲み、大盃に映る星々から勝機の程を占ったこの男、やがて腰をあげて小躍りする。なんと「今月今宵、樹齢三百年を超える桜を伐って護摩木【ごまぎ】にし、斑足【はんそく】太子の塚の神に祈願すれば、謀反の大願、成就ならん」という、注文は細かいがなんとも嬉しい星のお告げを、よりによって樹齢三百年を超える桜の下で得てしまったのである。
斑足太子とは、古代印度にあった摩訶陀【マカダ】国の王子のこと。后の華陽婦人にそそのかされ、千人の王を生け捕りにしてその首を塚の神に捧げようとするも、千人めの普明王に諭され悔悟し、王たちを解放して出家した。ここでの塚とは墳丘墓としてよかろう。そこに千の首を欲した華陽婦人の正体は、九尾の狐だったとされる。すなわち関兵衛もまた九尾の狐に操られているという裏設定が、占いによって示されている。こういう引用は洒落ている。
黒子の手から……じゃなかった、どこからともなく自慢の大鉞【まさかり】を持ち出してきた関兵衛、さっそくそれで桜を伐ろうとするのだが、振り上げるたび身が痺れてしまい次の所作へと移れない。そこに傾城【けいせい】薄墨が登場する。徳川時代に云うところの花魁である。
「誰だ? どうやってここに来た?」
「歩いてです。私、見た目のとおり傾城なんですけど、関兵衛さま、あの……私と付き合ってください」
書き手としてはなんとか自然な流れを作りたいのだが、実際にそう告白するのだから仕方がない。関兵衛にしても不自然すぎる流れだと感じているが、そこは男、傾城から交際を申し込まれたとあっては悪い気はしない。初めは探りを入れようとするが、そのうち調子に乗って彼女とじゃれ合い、郭【くるわ】の客たちへの嫉妬さえ露わにしはじめる。
ところで薄墨という名、先刻関兵衛が伐ろうとしていた目の前の桜に、かつて付けられていた名と同じである。その辺でなにか勘付きそうなもんだが、彼は面白い一致だとしか思っていない。薄墨は薄墨で、関兵衛が袖口から殺した男の片袖を落すまで、相手が恋人の仇だと気付かない……か、そういうふりをしている。殺された男は、偶然にも良岑宗貞の弟安貞だった。もはやこの種の偶然に文句を云ってはいけない。歌舞伎の偶然はおしなべて、前世の縁【えにし】という堅固な必然に支配されている。縁のない者同士が出逢ったり殺し合ったりするほうが、よっぽど話に無理があるのだ、本当に。
またもや落とし物で失敗した関兵衛、薄墨を威嚇しようとしてか、遂に自分の正体を明かす。「ふはははははは……なにを隠そうこの俺さま、天下を狙う大友黒主【おおとものくろぬし】さ」
薄墨も観客もあっと驚く場面なんで、ぜひ一緒に驚いていただきたい。怪しい男は極悪人で、しかも六歌仙の一人だったのだから。特撮よろしく衣装も変わる。
「お前も正体を現せ」と突然の等価交換を迫る黒主に、薄墨は応じて桜の精の本性を現す。黒主の場合もそうだが、荒縫いされていた衣装が黒子によって裂かれ垂れ下がると別の衣装の一部になる打【ぶ】っ返りというけれんが用いられ、これは掛値なしに見事なトリックだ。一秒くらいでそれが起きる。髪型も変わる。
ふたりの舞い……というか殺陣【たて】が始まる。大鉞を振りかざす黒主に、桜の精は桜の枝で対抗する。まあ細かいことは云うな、妖術も使っているようだし、ただの木の枝ではないんだろう。そしてその途中でおしまい。初演当時から二番目(興行の後半)だったらしいから、本当にそこでおしまい。
勝負の結末が描かれないのは様式美であるにせよ、桜の樹は伐られようとしたのだからとっとと正当防衛の逆襲に出ていればよかったわけで、なんでそのうえ恋人を殺されている必要があるのかだとか、安貞って植物と付き合ってたのかよといった、現代の我々の疑問や忿懣を超越したところに歌舞伎は屹立している……のだが、しかし一八世紀の人々ですら『関扉』のストーリィには苦笑したかもしれない。到底、筋書の巧みさに観客が膝を打つタイプの芝居ではない。辻褄なんかどうでもいい、スタア総出演の華やかな虚構さえ披露できれば、というのがこの『関扉』だ。
宝塚歌劇のショウみたいなもので、「すべて夢」と思って観るのが正しい。音楽と、役者の見得と、虚実を跨いだ強引な演出を楽しむための舞台である。物語の時点で薄墨桜が小町桜と呼ばれていることは、最初から立札が示している。しかも都に走った小野小町姫と、薄墨=小町桜の精は、同じ役者の二役なのだ。つまり観客の頭の中に、六歌仙の小野小町=小野小町姫=当代の人気役者=傾城薄墨=小町桜の精という長い等式が出来上がるよう、この芝居は仕組まれている。
小野小町の肖像画は後ろ姿が大半を占める。美しすぎて描けない、というわけだ。誰が着想した趣向かは分からねど、小町は後ろからしか描けない、すなわち後ろ姿の女性は小町、というルールは、じつに長きに亘って日本の絵画を支配してきた。たとえば徳川時代には当代の人気者たちを六歌仙に例えたナントカ六歌仙なる絵がおおいに流行ったのだが、そのうちに後ろ向きの人物がいるならば、それは必ず小町役なのだ。
類する現象は能にも見られる。小町を扱った七つの謡曲を「七小町」と称す。『草子洗【そうしあらい】小町』『通【かよい】小町』『雨乞小町』『関寺小町』『卒都婆小町』『清水小町』『鸚鵡小町』。このうち小町が美しい姿で出てくるのは『草子洗』と『雨乞』の二篇に過ぎない。あとは老いさらばえた姿であったり亡霊であったりする。
『関扉』に見られる大友黒主との敵対関係は『草子洗』に原拠している。歌合せに自信のなかった、とりわけ小町の実力を恐れていた黒主は、彼女の家へと忍び込み、その吟じている新作を盗み聞きする。さて勝負の席、小町の詠じた歌に黒主は「それは万葉の古歌だ」とけちをつける。万葉集を繙いてみれば、たしかにその歌が載っている。黒主が書き入れたのである。真相を見抜いた小町、草子を洗わせてもらうよう奏上する。願いは聞き入れられ、小町は銀の盥【たらい】に湛えた水でそれを洗う。彼女の歌は一字も残さず消え去り、彼女は神々と万葉歌人の加護に感謝する。若き日の小町が主人公らしい能動性を披露する、珍しい話だ。
『雨乞』のほうは、過剰な才色ゆえに宮中で疎んぜられ隠遁していた小町が、旱魃のさい朝廷から助けを求められ雨乞いの歌を詠むという、まあそれだけの話で、今は廃曲となっている。上演されなくなったという意味だ。
絵では後ろ姿、芝居に於いては老婆や亡霊。あまりに美しかったがゆえにその美を描かれないという、クレオパトラ七世も楊貴妃も辿りえなかった特異な宿命に甘んじてきた、逆説の美女が小野小町だ。クレオパトラの享年は四十前後、楊貴妃も三十代で歿している。対して小町は、七十代あるいは八十代、物の本によっては九十、百まで生きたとされており、この点も伝説的美女としては珍しい。六歌仙に数えられるほどの才気を誇り、美貌にまつわるエピソードにも事欠かなかった小町は、容色が衰えていたであろうその後半生をこそ注視された。諸行無常の権化として、のちの芸術家たちにインスピレーションを与え続けた。
もののついでに残りの「小町」の内容も示しておこう。『関寺小町』は、七夕祭の晩、逢坂の関寺に、かつて歌の道を極めたと噂の老女が招かれる話。住持との歌のやり取りからかの小野小町であることが知れ、集まった人々は色めき立つ。管絃にのせて童たちが舞う境内の華やかなさまに小町の心も浮き立つが、舞の手は忘却の彼方、足許すら覚束ない。夜明けを告げる鐘が鳴るや、自分の姿をはっきり見られるまえにと、杖にすがって草庵へと帰っていく。侘びしい。
背景を同じくしていると目せるのが『鸚鵡小町』で、新大納言行家なる人物が陽成院【ようぜいいん】の歌を携え、小町の許を訪ねてくる話。陽成院は百人一首「つくばねの峰よりおつるみなの川 恋ぞつもりて淵となりぬる」の人物である。行家から近況を尋ねられた小町、恥じる様子もなく物乞いをしていると答える。
雲の上はありし昔にかはらねど 見し玉簾【たまだれ】のうちやゆかしき
という陽成院の歌に返歌を求められると、
雲の上はありし昔にかはらねど 見し玉簾のうちぞゆかしき
と一文字だけ変えて返す。狂気の噂は真実だったかと吐息しつつ、
「こういう返歌の先例はあるのかね」と訊いた行家に、
「これを鸚鵡返しと申します。ぞをお返しいたしました」と小町は答えて庵に消える。
ただし折口信夫によれば、この物語は『十訓抄』にも見られる桜町中納言(藤原成範【しげのり】)のエピソードが、いつしか間違い小町の話として語られたものであろうとのこと。
『清水小町』は草庵を在原業平が訪ねてくる話。やっぱりここでも業平は小町より若く描かれているが、かろうじて史実と矛盾しない。なぜなら「ただ大悲をたのみ給え」と云い残して消え去る彼を、小町は観音菩薩の変化と信じるからだ。大悲とは仏の慈悲のことである。死んだ業平が訪ねてきた、仏のお告げに違いない、と解釈すれば筋が通る。これをきっかけに小町は諸国流浪の旅に出る……。
「おいこら、そこの汚い婆さん、腰を上げなさい。あんたが腰掛けているのはベンチじゃない。積まれた卒塔婆だ」
通りかかった僧たちに注意された乞食の小町、ゴルゴ13のような目付きで彼らを見返し、
「いまなんと?」
「卒塔婆だ」
「そのまえ。なんて呼びかけました?」
「……ちょっと汚いお婆さん」
「副詞や冠詞で逃げられるとでも? 云ってくれたね、生臭坊主。卒塔婆上等。私の心の華が手向けってわけさ。だいいち卒塔婆が横になり、私も一緒に休んでるわけですけど、なにか?」
「あのなあ婆……ご婦人、無学なあなたはご存じないかもしれないが」
「無学だと?」
「いやいや、たまたまご存じないのかもしれないが、卒塔婆というのは三摩耶形【さんまやぎょう】の一つ。つまり菩薩さまの持ち物なのだ」
「ほう」
「その形は地水火空風を現している」
「知ってますとも。地輪、水輪、火輪、空輪、風輪で五大五輪ってやつね」
「ぬ」
「まさしく人体がそうなんですけど。頭と両手両足で五輪と云うのはご存じですよね。では私も卒塔婆と同じく有り難いんじゃなくて?」
「口の減らない婆さんだな。受けて立とうじゃないか。卒塔婆は一見すれば三悪道、すなわち地獄道、餓鬼道、畜生道から逃れられると云われている。そんなご利益があんたにあるとでも?」
「あら、あっさり墓穴を掘ったわね。一念発起菩提心、すなわち悟りを求めれば世人を救えるとお説教してまわっているのは、どこのどなたたちかしら。だったら私にだって卒塔婆並みのご利益。これ、私の主張じゃありませんから」
たじたじとなる僧たちに、小町、さらに得意技で追い討ちをかける。
「極楽の内ならばこそ悪しからめ、外は何かは苦しかるべき」
極楽でやったなら悪いことなんでしょうけど、その外は(卒塔婆)べつだん問題ないのでは? という戯歌である。
「わ、アドリブでそこまで。なんなんだ、その溢れんばかりの教養とスピリチュアルパワーは!? まさか美輪明宏が芝居してるんじゃないだろうな」
「さほどの者じゃございませんけどね」と勝ち誇る小町。
「まさかあんた、噂の……えっ、まだ生きていたのか。これはお見逸れしました」
掌を返したように恐縮し、地に膝を突き三度の礼で表敬する僧たちに、
「おほほほほ、おほほほほほほ、おほほほほ、おほほほほほほ、おほほほほほほ」と小町は三十一文字の高笑いを返し、そのまま発作へと至る。とつぜん僧へと詰め寄り、「なんかちょうだい」
「こ……今度はなんですか」
「おなかが空いてるのよ。ねえお坊さん、なんかちょうだい」
じつは小町、若かりしころ百夜通いを命じて苦しめた、深草少将の怨霊に祟られている。百夜欠かさずうちの榻【しじ】まで通ってきたら、結ばれてあげても宜しくてよ、と高飛車なことを云った。「徒歩でね」
榻というのは牛車のスタンドである。乗降時の踏み台ともする。諦めさせようという心算からの言葉だったが、少将はこれを真に受け、本当に百度通いを始めてしまった。雨の夜も雪の夜も蓑笠をつけて近からぬ道のりを通い、榻に榧【かや】の実を置いてその証拠とした。しかし満願成就の百夜め、雪のなかで行き倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまう。そうしたさまを少将に憑依された小町が再現するのが、『卒都婆小町』。卒塔婆ではなく卒「都」婆となっているのは、都落ちを意味しているのだろう。
『通小町』はその続篇と云える。比叡山麓の山里八瀬で夏安吾【げあんご】の籠もり修行をしている若い僧の許へ、連日、食糧や薪を届けてくれる者がいる。ときおり独り言を云っているので女との見当はついている。僧に名前がないので、ここでは仮に泰水【たいすい】とでもしておこう。
「拾う爪木も焚き物の、拾う爪木も焚き物の、匂わぬ袖ぞ悲しき」
という独り言が今日も聞えてきた。薪を拾って焚いたところで袖にゆかしい香りが移るじゃなし、あーあ、お香が懐かしい……といった意味だ。急いで草庵を出た泰水、荷物を置いて帰ろうとする老女の後ろ姿を目にする。
「マダム」と呼ぶと、
「はいはい」と振り返った。
「これまでお礼を申しそびれてきました。女性の細腕には重たかろう数々の贈り物、いつも本当にありがとうございます」
答えて女、「賤しい女が摘みなれた、根芹や若菜、我が名も知らぬほどカジュアルな木の実、べつに重くはございません」
この実とこの身を掛けている。この婆さん、只者ではないと睨んだ泰水、
「普段、どんな木の実を集めていらっしゃるのですか」と問うてみた。
すると女、雅な木の実尽くしの謡を披露する。「拾う木の実は何々ぞ。拾う木の実は何々ぞ。いにしえ見慣れし車に似たるは、嵐に脆き落椎【おちじい】。歌人の家の木の実には、人丸の垣穂の柿、山の辺の笹栗、窓の梅、園の桃、花の名にある桜麻の、苧生【おふ】の浦梨なおも有り。石櫧【いちい】、香椎【かしい】、真手葉椎【まてばしい】、大小柑子【だいしょうこうじ】、金柑【きんかん】。あはれ昔の恋しきは、花橘【はなたちばな】の一枝、花橘の一枝」
人丸は柿本人麻呂、山の辺は山辺赤人を指しているようだ。すっかり感心して、
「お名前を」と尋ねた泰水に、
「恥ずかしいので小野とは申しません」と、教えたいんだか教えたくないんだか。「薄の生える市原野辺に住む姥でございです。お弔いをお願いします」
女の姿はかき消えた。
「あ、幽霊だったのか」そう、この時点で小町はすでに死んでいる。「小野……小野……あ」
泰水はかつて先輩僧から聞かされた昔噺を思い出す。在五中将すなわち在原業平が野ざらしの髑髏となった小町の姿を予見し、その「秋風の吹くにつけてもあなめあなめ」という呟きに下の句をつけて弔いとしたとか。最前の木の実尽くしの教養はいかにも小町に相応しい。すると業平の歌では成仏できなかったのか?
泰水はいったん寺へと下りて、くだんの先輩僧に相談する。こちらの僧の名は仮に啓文【けいぶん】とでもしておこう。
「小野小町の亡霊が市原野に? それは供養をせんといかんな」と啓文。
「一緒に行ってもらえますか」
「若い姿かいな」
「腰の曲がった婆さんです」
「気が進まん。独りで行って経を唱えてこい」
泰水は手を拱【こまね】いて、「そうしてやりたいようなやりたくないような、不思議な心地なんですよ。成仏させちゃったら、もう食糧を届けてもらえないし」
「その現金な思考回路は、仏に仕える身としてどうなんや」
「どっちが現金なんですか。婆さんと知った途端に及び腰になっちゃって」
「お前、もうその婆さんに取り憑かれてるんや。ふらりと現れて仏門に入って、つらい修行も涼しい顔でこなしてきたお前を、つくづく不思議な奴やとは思うてたが、とうとう小野小町の亡霊まで呼び寄せてしもうたか」
「すみません、どういう因縁なんだか……俺、昔の記憶がほとんど無いんですよね」
「お前の夏安居が終わったら終わったで、婆さん、この寺まで通ってきかねんな。本人の希望でもあることやし、早めに供養しとくか。しかし在五中将が髑髏を見たのは奧州やろうに、なんでまた都の近くに迷い出てきたかいな」
「そこも解せないんですよ」
ふたりは草深い市原野へと出向き、この辺でよかろうという場所で経を唱えはじめた。
「……ありがとうございます」と、風が小町の声を運んできた。「いっそのこと戒を授けて仏弟子とし、きれいに成仏させてくださいませ……」
「ほほう、亡霊とは思えん殊勝な心掛け。小野小町ともあろう御仁が改悔のうえ御仏の戒めをも受け容れるとあらば、きっと迷わず三途の川を渡れましょうぞ」と啓文が声を弾ませるかたわら、
「いや、それは許さん」と叫んだのは泰水である。
啓文が驚き振り返り見れば、泰水はまるで別人の形相で歯がみをしている。「こうしてふたり、苦界を彷徨うさだめもつらくてならんというのに、このうえ貴方ひとりが救われようとなさるか」
「お前……誰なんや」と驚く啓文。
「自分だけ受戒し極楽浄土へ旅立って、私には三途の川に沈みはてろと仰有るか」
「泰水……お前も亡霊やったんか」
古霊が自らのなんたるかを忘れ、無意識のうちに仏へと縋っていた姿が泰水であり、生きていた頃の彼は、深草少将その人であった。別個に少将の亡霊が現れ出でるのが舞台での通例なのだが、こちらの異説のほうが遥かに面白いし辻褄も合っている。小町の霊が泰水に連日供物を捧げていたのは、かつて自分が死に至らしめた男だったからだ。
「逝かせぬ」
と泰水が空を掴めば、小町がひいいと悲鳴をあげる。泰水には小町の姿が見えていると思しい。
「……もはや私は山の鹿【かせき】、いかに招かれようとて留まりはしません……」
「さらば私は煩悩の犬となり、たとえ鞭打たれようとも離れまいぞ」と泰水は、憤怒の形相のまま涙を流しはじめた。
小町が自分を鹿に、少将が自分を犬に例えるこのくだりが素晴しい。かたや度が過ぎた高慢の罪、かたや死に際の恨みによる妄執から、ともども畜生道に堕ちているのである。
「まあまあご両人、せっかくここに坊主がおるんやから、生前のことを懺悔なさってですね、建設的方策を模索してみようやないですか」
この啓文の提案を聞いてか聞かずか、
「……貴方を愚弄する気はありませんでした。ものの弾みで口にした百夜通いのお願いでしたが、夕暮れごとに貴方への想いが募ったもの……」
「空言を。優雅に月の出でも待っていたんだろうよ。こっちはもう、月があるならまだましで、雪が降れば身に積もるわ、雨が降れば鬼でも出てきそうで、半べそをかきつつ通い詰めていた」
「……榧の実を見ての暁ごと、貴方のご苦労を察して思い煩いました……」
「鶏が啼こうが鐘が鳴ろうが欠伸を返し、そのうち気分壮快にラジオ体操でもやっていたことだろう」
と亡霊同士、勝手に痴話喧嘩をしている。
「泰水お前、百夜通いで有名な深草少将はんやったんか。未だ成仏でけへんとは、いったいどないなふうに亡くなったんや」
問う啓文をおもむろに亡霊が見返すや、その背後に雪の夜のパノラマが広がった。
「今宵ぞ満願」と誇らしげに発した亡霊、いつの間にか被っていた笠、纏っていた簑を投げ捨て、風折烏帽子【かざおりえぼし】に花染めの色襲【いろがさね】、裏紫の藤袴、紅の狩衣【かりぎぬ】という姿に変じ、ざっくざっくと深い雪を踏みしめはじめた。
「伊達の極みやなあ。雪のなか、そないな恰好で行かはったんか、晴れ姿を小町はんに見せよう思うて……つくづく惚れてたんやな」
「酒でもてなされるかもしれないな」と少将、ふと立ち止まり微笑まじりに独りごちた。やがてかぶりを振って、
「もてなされたくて行くんじゃない。この百個めの榧の実を届けるためだ。ただ愛しい人への約束を守るためだ。たとえ月の盃で勧められようとも、もてなしは受けまい」
「そないな立派な心掛けでの途上で死なはったんか。さぞ悔しかったやろな」
少将の侠気【おとこぎ】に啓文の視界は潤んだ。小町もすすり泣いている。
「……ごめんなさい、ごめんなさい。貴方が苦界を彷徨われるかぎり、私もこちらに踏み留まりましょう……」
「いや私が思うに、おふたりはもう立派な仏弟子や。極楽浄土で仲良うなされ」
そう啓文が高らかに発するや、雪野原も少将の姿も掻き消え、小町の声も遠ざかり、ただ茫々たる夏草が風に揺れているばかりとなった。
『卒都婆』の小町も『通』の小町もどこか浅はかで、その教養も美も、坊主相手の屁理屈や少将の妄執から類推するほかないという気の毒な拵えになっている。小町の美は描きえないというルールに支配されている。この故習が募らせてしまった大衆の鬱憤を晴らそうとしたのが、小町尽くしの『関扉』であるとは申せまいか。
繰り返しとなるが『関扉』に小野小町その人は登場しない。名前が合致しているだけの姫君、傾城=桜の精、それらを演じる人気役者、いずれも水面に映ったかのような小町であって、宮中に華やぎを添えるでも歌を詠むでも、かぐや姫よろしく男たちに無理難題を押し付けるでもない。小町であって小町ではないからこそ、芳年は遠慮なくその顔を描けた。装いはまるきり花魁である。現代でいうならば歴史上の人物に露出度の高いイヴニングドレスを着せるような感覚であり、メタ物語『関扉』が、このぶっ飛んだ表現を可能とした。なんだかんだで歌舞伎の破壞力は凄まじい。
「やりたい放題」と世人に苦笑されがちなこの一連の駄文――あやしよしとし――だが、なに、能だって歌舞伎だって錦絵だって、やりたい放題の蓄積なのだ。時の移ろい(花の色はうつりにけりないたづらに)と共に面白味の大半は風に吹かれ、比重の高い僅かな粒だけが残り、それが積もって砂丘となって、我々はその上に寝転んでいる。