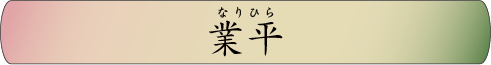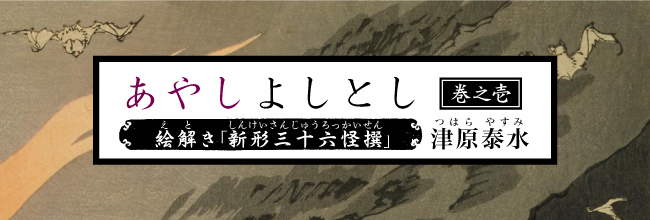この画のタイトルは長い。長すぎるので『新形三十六怪撰』が上梓された当時の目録には、ただ「業平」とだけ記されている。本当は「秋風のふくにつけてもあなめ/\ をのとはいはしすゝき生【はえ】けり 業平」と、歌一首と署名がまるごと題名として付されている。そうは読めない? 致し方ない。仮名の表記が未だ統一されていない時代の、現代で云うところの「変体仮名」が用いられているのだ。
平仮名が漢字の省略形であることはご周知のとおり。「あ」は「安」の略、「い」は「以」の略。どうも自分は字が下手糞でとお困りの方は、なるべく元となった漢字を意識して書くようにするといい。途端に上手くなる。読者の利便のため、いっそのこと五十音の字源を全て列記しておこう。
安、以、宇、衣、於。
加、幾、久、計、己。
左、之、寸、世、曾。
太、知、川、天、止。
奈、仁、奴、祢、乃。
波、比、不、阝、保。
末、美、武、女、毛。
也、以、由、衣、与。
良、利、留、礼、呂。
和、爲、宇、恵、遠。
无。
重複があるのは、近世になって近い発音のものが整理されたからだ。さらに現代に於いては「や行」の「ゑ」や「わ行」の「ゐ」もほぼ絶滅してしまった。とまれ上の表から、「あ」と「お」、「き」と「さ」、「け」と「は」、「し」と「も」が親戚でもなんでもないことがお分かりいただけるだろう。もっとも「た」と「な」、「ぬ」と「め」は、ご覧のとおり親戚関係にある。ちなみに「阝」は「部」の旁【つくり】で、要するに「部」が省略されて「阝」となり、更に「へ」へと突然変異を果たしたわけである。
明治三十三(一九〇〇)年の小学校令以前、平仮名はこの何倍もあった。そのとき採用されず以後頽れてしまった仮名文字群が、今は便宜上「変体仮名」と呼ばれている。芳年の画のタイトルとなっている歌の、現代人には読みづらい文字の字源を示すとこうなる。
秋風能ふく耳津けてもあなめ/\ をの土者い者し春ゝき生希里 業平
(秋風のふくにつけてもあなめ/\ をのとはいはしすゝき生けり 業平)
ほぼ暗号だが、昔の教養人にはこれが読めた。詠み手は業平となっている。云うまでもなく六歌仙のひとり、稀なる美男子として名高い恋歌の達人、在原業平【ありわらのなりひら】――ここに描かれている人物は彼だ。明治時代の書生みたいな髪型をしているけれど業平である。休憩中の噺家のようにも見えるが、断じて業平だ。
じつは彼、今は部屋着でくつろいでいるのであって、衣桁【いこう】に掛かった外出着が背景に見える。その下に置かれた笠によって旅先にいることが示されている。時代を超越した髪型にもじつは理由がある。平たく云えば、女で失敗してしまった。
相手はのちに清和天皇に見初められ、皇太后の地位にまで登りつめる藤原高子【ふじわらのたかいこ】。藤原家にとっては才色兼備の秘蔵っ娘であり、彼女にたぶん「忘れては夢かとぞ思ふ思ひきや、雪踏みわけて君を見むとは」なんぞと囁きかけて手を出した業平に、一族は怒り狂った。彼を引掴まえ、その髷を切り落としてしまった。
業平といえばその生き様が『源氏物語』執筆の参考にされた人物であり、貴族社会では通い婚の重婚が基本であった時代に於いて、彼のふるまいがさして放埒だったとは云えない。ひたすら相手が悪かった。家柄といい美貌といい、いずれ后となることを嘱望されていた女性であって、近年でいえば……いや、これは記すまい。誰を挙げても角が立つ。
当時としてはやけに過激な髪型にされてしまった業平、これではどこにも夜這いがかけられん、と傷心の旅に出る。「たとえどんなに流れていても、お前が俺には最後の女」と詠んだか詠まなかったかは定かではないが、みちのくひとり旅である。先人の名歌が詠まれた地を訪ね歩いたとも云われている。
流れ流れて最果ての、陸奧の国は八十島【やそしま】の地に宿を求めた。彼の典雅な装いに、あるじが驚いている。笠を脱いだ瞬間はもっと驚かれたが、
「都の流行りなのだ」と誤魔化した。
「斬新でございますな」
「涼しくていいぞ」
「その涼しいヘアスタイルで、あえて秋風びゅうびゅう、薄【すすき】ぼうぼうの当地へとようこそ」
「嫌味ったらしいな、君は。ほかの宿にしようか」
あるじはうくくと咽を鳴らして、「見つかりますやら」
業平は鼻の穴を広げた。「ここに泊まる。泊めてくれ」
「もう一声」
「泊めてください」
「宜しゅうございます。お一人様、ご案内」
このサーヴィスも景観も悪い宿屋で夜を過ごしている業平の耳に、秋風が運んできた歌が「秋風のふくにつけてもあなめ/\」なのだが……さて困った。
結論から云えば、歌っているのはこれまた六歌仙の一人、絶世の美女として名高かった小野小町――その髑髏【されこうべ】だ。当時としては長生きをした人物のようだが、その晩年は能『卒都婆小町』に見られるように流浪の乞食であったとされる。小野一族にゆかりの深い陸奧の国まで流れ着いたものの、野垂れ死んでしまい、成仏できずに迷っているというのが『無名草子【むみょうぞうし】』などを典拠とする「業平」の設定である。
ところが、ところが! 小町と業平は同世代なのだ。同じ天長二(八二五)年の生まれだという説さえあり、歌舞伎『六歌仙容彩【ろっかせんすがたのいろどり】』では若い男女としての絡みを披露している。五十代の半ばまでしか生きなかった業平が、老婆となり遺体となり、果てに野ざらしの髑髏と化した小町と相まみえる可能性は、皆無。業平がみちのくひとり旅をしていた頃、小町はぴんぴんとして後宮にいる。
翻って「業平」の世界観に於いては、地元の連中までもが小町を昔の人として、「ああ、その髑髏は小町のものでしょう」と見当をつけてしまう。どうしたものか。
いったんこの矛盾を離れ、風に乗ってきた歌に注目してみよう。「秋風のふくにつけても」に解釈は要るまい。問題は「あなめ/\」だ。ものの本には「ああ、眼が痛い」という意味だとある。他の文献をあたっても似たようなことが書かれている。ところが調べても調べても、いわゆる「業平」以外での用例が見つからない。このことを逆用できまいか?
「あなめあなめ」と聞いた業平、かつて口説き落とせずそのかんばせを覗き見ることも叶わなかった、小野小町を思い出す。かつて彼女がこちらに背を向けたまま、袖口で顔を押さえて発した文句が、まさに「あなめあなめ」であったとしてみる。
「あな眼、あな眼」すなわち「ああ眼が、ああ眼が」と聞いた業平、
「眼にごみでも入りましたか」と心配するも、
「やがて解決します」と小町は素っ気ない。「闖入者がお帰りになれば」
ナルシストの業平、この彼女の言葉を都合良く解釈した。俺の美貌が……そんなにも眩しいのか。
恋歌合戦に至ることはなく、すなわち夜這いには失敗したものの、悪い気はしなかった。さすが当世きっての歌の達人、男の振り方も捻りが効いているなどと感心しながら、閨房を去った――。
まさか、あの小町がこんな僻地の薄の原に?
業平、はたとあることを思い出し、膝を叩いた。小町の曾祖父小野岑守【おののみねもり】は、かつて陸奥守だったではないか。彼が他家の来歴に詳しいのは、その息子、小町にとっては祖父にあたる小野篁【たかむら】が、飛切りの有名人だったからだ。まず見た目が凄い。身長一九〇センチに及ばんとする大男である。公卿の筋にもかかわらず若かりし頃は武芸にしか興味を示さぬ暴れん坊、しかし「なぜそんなふうに育ったか」という嵯峨天皇の嘆きを耳にして心を入れ替え、学問に努め、やがて文筆で名を馳せる。しかし反骨精神は収まらず、よりによって朝廷をからかった詩を公表し、隠岐に流されたりもしている。のちに詩才を理由に免罪されて朝廷の要職に戻るも、豪腕政治家として狂った小野――野狂【やきょう】と呼ばれた。
「やはり小町の声? 小町がこの地に?」
翌朝、宿のあるじに尋ねてみた。「つかぬことを問うが、この辺に陸奥守かそのご血縁が建てられた、山荘でもありはしないかね」
「はあ? 山荘でもペンションでも、もし見つけたなら教えてください。こんど泊まりに行ってみますんで」
「君はじつに性格が悪いな」
「よくそう云われます」
この宿のほかに泊まれるような場所がないと知るや、胸騒ぎがした。履き物をはき笠をかむって宿を出る。外は朝霧に覆われていて、ひどく視界が悪かった。あとさきなく薄の原に踏み出してしまったことをちょっとばかり悔やみ、いつ引き返そうかと迷いながら、そろりそろり、昨夜の風上と思しい方向へと歩む。
都で恥をかくくらいなら、いっそみちのくひとり旅、という程度の矜恃はあるが、しょせん根は軟弱な色男、早々に不安になって宿のほうを振り返っては、なにも見えずにしょんぼりとする。これほどの濃霧が長く続くはずはないという楽観的予測のもと、もうすこし歩んでみては、すぐまた「なにやってんだろ、俺」と後悔しはじめる。
乳白色の世界から、唐突に薄の群れが現れ出でては行く手を阻むばかりの、悪夢めいた出口のない世界に、いつしか彼はいた。
魔物の手よろしく不意に現れ出でた薄の穂に顔面を撫でられ、目を瞬かせながら思わず、
「あなめあなめ」と呟いた。これに応じるように、
「……あなめあなめ」とすぐ近くで女の声がし、業平は震え上がった。
風が出てきた。これで霧が晴れるとほっとした。今の声はきっと気のせいだ。そう思い込もうとしたのも束の間、
「秋風の吹くにつけても、あなめあなめ」とより明瞭に聞えてきて、あまっさえ、ようよう見えはじめた足許に、彼は白い塊を見た。腰を屈めて観察するまでもなく、明らかにそれは人間の頭蓋骨であった。
見下ろしていて気分のいい物ではないが、そこは歌人、詠んでいたのはこの人物かと察するに、むしろ落ち着きが生じてきた。いつ頃から野ざらしになってきたものか、両の眼窩から薄が生えて高々と伸びている。だから風が吹くと痛いのか。それにしても小町と口癖が同じとは、なんとも風雅な髑髏である。
しばしその哀れなさまを見つめたあと、
「下の句を付けてほしいのかね」と相手に問い掛けてみた。
目の錯覚か、微かに白い塊が頷いたような気がした。
「分かったよ」と頷く業平。こうなると天才歌人の独擅場、即座にアドリブで、「……小野とは云わじ、薄生えけり、は如何だろうか」
謎かけのような上の句に対して、この下の句は知的なダブルミーニングになっている。「小野」とは元来「お野」であり、野原を指す。「野原とは云えない。だって薄でぼうぼうだ」という意味と、「小野小町とは呼ぶまい、薄を生やした貴方を」という意味とを掛けてある。
……ずざっずざっという奇妙な音が、後方から聞えてきた。業平が身構えていると、晴れきらぬ霧のなかから、なんだか奇妙な風体の若者が姿を現した。鎌で邪魔な薄を払いながら、こちらへと近付いてくる。あちらはあちらで、ふと霧のなかに生じた業平の姿に驚いているふうである。
「宿からの迎えか」と声をあげてみた。
「宿? 旅館のこと?」と若者は不思議なイントネーションで問い返してきた。「この辺に旅館なんざ一軒もないけど」
業平は首をかしげながら、「ところで君、ここに髑髏がある。このままじゃあ、いくらなんでも可哀相だ」
「ああ、こんな所に」と、若者は業平の足許を覗いた。「こりゃたぶん、小野小町とかいう乞食婆さんの――」
そのときごおおと空が鳴り、追って強風が薄の原を襲った。業平は笠を両手で掴み、目を閉じてそれを凌いだ。
風が弱まり彼が目を開けたとき、霧はすっかり薄れて、辺りに若者の姿はなく、足許の気の毒な髑髏も消え失せていた。穂の波の向こうに宿屋の屋根が見えた。さして遠くには来ていなかったのだ。
髑髏の主は成仏してくれたのだろうかと考えながら、薄の群れを躱し躱し宿屋へと引き返す。その途中、卒然と、自分が霧のなかで未来をかいま見ていた可能性に気付いた。