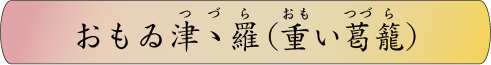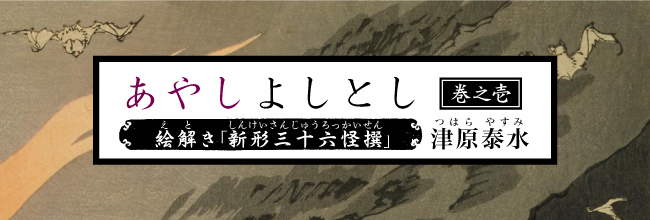北陸で語り継がれてきた「舌切り雀」は、知れば知るほど不思議な、かつ複雑な構造を擁した物語であり、民話というより神話と目すべきかと思う。まず主要キャラクターである爺【じじ】と婆【ばば】と雀が、いったいどこの誰なんだか判然としない。この解釈から入る。
大切な「糊」を舐めてしまった雀の舌を、婆は切る。そんなことをしてしまったら、雀はもはや囀【さえず】れないどころか死んでしまうだろう。成功率は低いらしいが、舌を噛み切って窒息するという自殺法は古くから知られている。つまり婆は雀を殺したのである。舌というのは筋肉の塊で、断裂すると強く収縮し、気道をすっかり塞いでしまう。これは人の場合であるが、鳥類に当てはまるかどうかを実験してみるには及ばない。のちの場面にて、異界でのこととはいえ雀たちは人家に人として暮らし、爺婆はそれを当然として驚かない。つまり、人が敢えて雀として言い伝えられたのだと推察される。雀は人である。
舌を切られる舌切り雀と、羽根を切られる羽根切り雀、二羽が登場するヴァージョンも広く語り継がれている。複数の者が惨たらしい殺され方をした、ということになる。その行為を経て平然としていられる婆は、権力者だ。爺も同格か、それ以上の存在だろう。一応、夫であるとしておこう。
では雀たちとは? 爺がその魂の行方をよく知らないことから、遠方で生まれた存在であると察せられる。あっさり命を奪われていることに鑑みて、戦に敗れた一族の生き残りだと推断してみる。勝った側の寛容により爺と婆に仕えていたが、なんらかの盗みをはたらいてしまい、婆の命で惨殺されたのでは――と。
可愛がっていた雀たちを失った爺は、その俤【おもかげ】を求めて旅に出る。死んだ雀に会いにいくのだから、実際の目的は墓参である。かつての敵地に足を踏み入れるに際し、彼は身分を隠しての一人旅を選んだ。
旅慣れないがゆえ、なにかと道に迷う。雨風が老骨にこたえて、ときには意識が朦朧となる。住み慣れた地を遠ざかるほどに言葉が通じにくくなり、自分に向けられる人々の視線は冷たく思え、他郷にいるんだか冥土にいるんだか分からなくなってくる。
明治以降の、子供向けに酷い描写を排除した版では、この道中の爺の苦労が割愛されるか穏便に改められている。本当は凄まじい虐待に遭っている。
ある語りによれば、牛方に雀の郷を尋ねたところ牛の糞を突き出される。言葉の訛りが強くてよく分からないが、ジェスチュアから察するに食えば教えてやると云っているらしい。いくらなんでも無体な条件だ。ところが雀会いたさに、爺はそれを貪り食ってしまう。この辺りで彼はもはや異界を彷徨っている。
雀の行方だったら馬方に訊けと教わり、今度はそれを探し求める。見つけた馬方に雀の郷を問うと、彼は桶に馬の小便を汲んできた。
「それを飲め……という話なんでしょうな」
馬方は嬉しげに頷く。
飲んだ。なんとかかんとか飲み干した。しかし得られた答はまた、誰某に訊いてみろ、である。
馬の血を飲まされるという語りもある。やや穏便に、馬の洗い水、牛の洗い水、菜の洗い水を、大量に飲み干すよう強要される版もある。ともかくそんな地獄巡りのような旅の末、爺はようやっと雀の郷たる竹林に辿り着く。
爺がそこに見たのは墓標ではなく、赤い前掛け姿で米を搗【つ】いている、つまり臼の中の米を棒で突いて糠を落している、活き活きとした舌切り雀の姿だった。
「お館さま……お館さま!?」彼の姿に気付いた雀が、悲鳴のような声をあげながら駆け寄ってきて、姉様被りにしていた手拭いを取る。
「ここでは喋れるのか」と爺の目に涙がにじんだ。「よかった」
「どうやってここへ」
「さあなあ」と爺は目尻を拭いながら笑った。「いつ死んだんだか、それとも旅の途中で夢をみているんだか」
「大変でございましたね」雀の目にも涙がうかんでいる。婆の仕打ちとは裏腹に、爺はいつも彼女らを庇っていた。「本当に……本当に、大変でございましたね」
「うちの婆がお前たちに非道いことを。それを一言詫びたくてね」
「私たちが悪いんです」
「いや、お前たちを飢えさせた婆が悪い。本当に申し訳ないことをした。ここがお前たちの故郷か」
雀は竹林を見渡して頷き、「ええ……こうあるはずだった、私たちの故郷です、焼け野原でも墓標の林でもない。妹を呼んできますね」
彼女は家へと入り、やがて羽根切り雀を伴って外に出てきた。
「お館さま」とそちらも泣きはじめている。「機織りに夢中で、お出ましに気付きませんでした」
「ちゃんとある」爺は彼女の両手に触れた。「今はまた機を織れるんだね。よかった。本当に来てよかった」
雀たちの血縁の老若男女が集められた。理不尽な戦や、雀たちに対する仕打ちへの恨み言を聞かされるかと思いきや、よくぞここまでおいでになったと旅の苦労を犒われ、白い米や魚でもてなされた。爺はありがたく頂いた。
腹が膨れて眠くなった。旅の疲れがどっと出てきたようで、今しも瞼が落ちそうだ。
「お布団をご用意しますから、今夜はゆっくりお休みになってください」と舌切り雀が云う。
「ありがとう」と爺は頷き、そして訊いた。「私はここから帰れるんだろうか」
「お帰りになりたいですか」
「そうだな……出来ることなら。嫉妬と暴力に満ちた非道い世界だが、だからこそ、私にはやらねばならないことがたんとある」
雀は深く頷いて、「お館さまはあちらに必要な方です。無事にお帰りになれますよう、皆と相談しておきます」
翌朝、出立の支度をしている爺のところに、雀たちが古ぼけた葛籠を一つずつ運んできた。
「どうかお持ちください。無事にお帰りになるためのお守りとなりましょう」
葛籠の大きさに爺は困った。「年寄りの一人旅に、あまり荷物は増やしたくないな」
「お持ちなら、道中お迷いになりますまいとのことです。せめて片方でもお持ちください」と雀たちが傅く。
爺は仕方なく、「では、軽いほうだけ」
「どちらも似たような重さだと思いますが」
試しに抱えてみると、たしかにどちらも大した重さではない。片方など、何も入っていないかのようだ。そちらを選んだ。葛籠を選ばれなかった羽根切り雀は、がっかりした顔付きでいた。
「お志だけ、ありがたく頂いておくよ」と爺は彼女を慰めた。
「あちらに着かれるまで、お開けになりませんよう」と舌切り雀から強く云われた。
「分かったよ」
爺は帰途についた。この復路は天候に恵まれ、葛籠を背負っているにも拘わらず足取りは軽かった。中を覗いてみたいという思いが無いではなかったが、雀との約束を反故にする気にはなれなかった。
途中、往路の自分に小便を飲ませた馬方や、糞を食わせた牛方の姿を見た。しかし道順を問うまでもなく、怯えたような顔付きで進むべき方向を示してくれた。爺は深々と頭をさげた。
往路との違いは葛籠の有無だけ、すると彼らが畏怖したのは葛籠だ。中身はなんだ? なんだろう、と考え続けているうち、存外にあっさりと、見知った景色のなかを歩みはじめていた。もはや故郷である。
擦れ違う人々が、爺を誰とも知らずに挨拶してくる。「爺さん、重くないかね」と心配してくれる者もいる。あの美しい竹林には敵わないが、こちらはこちらで、そう悪い場所ではないのだ。
殊勝な心持ちで館に帰り着いた爺は、葛籠を大切に下ろし、おっかなびっくりその蓋を開けてみた。手紙と、紙に包まれたなんらかの種子が入っていた。それだけだった。
手紙は舌切り雀からで、館での楽しかった思い出が綴られていた。つらかったことも多かろうに、それらにはいっさい触れていなかった。
「もう一つの葛籠に入っている反物は、妹が織ったものです。金子【きんす】に換えて、戦で亡くなった方々のご供養にお使いください」とあるのを読んだとき、ああ、持ち帰らずに申し訳ないことをしたと思った。これからも懇ろな供養を続けねば、との決意も強くした。
手紙には更にこうあった。「こちらの葛籠には瓢箪の種を入れておきます。お庭に植えていただき、もし立派な瓢箪が成りましたら、瓠【ひさご】にしてお側にお置きください」
雀からの返礼を「一分小判やら何やら」の宝物ではなく、ここでは敢えて瓢箪の種とした。鎌倉時代に成立した『宇治拾遺物語【うじしゅういものがたり】』にある「雀報恩事【すずめほうおんのこと】」通称「腰折れ雀」からの引用である。金銀財宝よりそちらのほうが面白いし、物語内の論理として適切に思える。雀がくれた金銀に善人が小躍りした、というのはどうも納得がいかない。「雀報恩事」も「舌切り雀」のヴァリエーションに違いなかろうし、雀が二羽ヴァージョンとの絶妙なアナロジーも観察されるから、意図的にミクスチュアしている。
なお「雀報恩事」の善玉悪玉は、どちらも「六十ばかりの女」すなわち婆さんだ。訓話的性格の強い『宇治拾遺物語』で、男女のどちらが痛い目を見たか、ではまとまりが悪かったと思しい。また冒頭にて「舌切り雀」を神話的と称したのは、爺と雀たちの関係性にエロティックな要素が垣間見えるからでもあり、これまた訓話には不都合だ。
「雀報恩事」の善玉老女に植えられた瓢箪は、芽吹いてすくすくと成長し、秋にはたくさんの実をつけた。これを彼女は隣村の人々にまで振る舞う。食用としてだ。えっ瓢箪って食えるの? という疑問をいだかれた方は多かろう。基本的に食えない、というか食うな、が答だ。苦味成分のククルビタシンが食中毒を引き起こす。しかしこれが少ない変種もあって、一例が夕顔、その一種である丸夕顔【まるゆうがお】の実を薄く削って乾燥させると、お馴染みの干瓢【かんぴょう】と相成る。
爺の館の庭に植えられた瓢箪の実が食えたかどうかは別にして、成った実のうちの大きな幾つかから、彼は雀の指示どおり瓠を拵えた。糸瓜【へちま】から束子【たわし】を拵えるのと同様、水に浸け柔らかい部分を腐敗させて悪臭と闘いながら取り除いていく、なかなか厄介な作業だ。さらに乾燥、塗装を経て、我々が通常「ひょうたん」と呼ぶ、あの水筒状の容器が出来上がる。
雀たちとの思い出の品とも云える瓠を、あるとき爺が手にとると、なにも入れた覚えがないのにざらざらと音がした。逆さにして振ってみた。白い米が出てきた。ほかの瓠も確かめた。僅かずつではあったが、どの瓠からも米が出た。手の皮を剥きながら連日米を搗いていた舌切り雀からの、これが墓参への返礼だと思うと、涙が出た。きれいに出して茶碗に溜めておいた。
ところが翌日になると、また米が溜まっていた。驚きと喜びから、爺はそのさまを家人たちに披露した。「またまた。俺たちをびっくりさせようとして、仕込んでおかれたんでしょう」と疑う者がいたので、「では持ち帰って自分で試してみなさい」と彼らに瓠を配った。
家人たちの許でも同様の奇蹟が起きた。畏れ多いと瓠を返そうとする者もいたが、爺は「よかったね。有り難く頂きなさい」と受け取らなかった。
話は婆に伝わった。普段は汚らわしいとばかり口をきこうともしない女が、久々に爺の前に姿を現し、根掘り葉掘り瓠の来歴を尋ねた。すこしでも雀たちを見直してくれればという想いから、爺は正直なところを語ったが、
「なんでもう一つの葛籠も持って帰んないの。そっちは私へのお土産じゃないの!」と怒鳴りつけられた。
「いやいや、あっちにはまた別の目的があって――」
「私は私で、あの子たちをそれなりに可愛がっていました」
「殺しただろ」
「癖の悪い舌を切れとか手をちょん切れといった、文学的表現を理解しなかったのは家来たちです。私は殺していません。あの子たちには感謝されているはずです。なんなら私も墓参して、葛籠を貰ってそれを証明して見せます」
「冥土への道行きはしんどいよ。とうていお勧めできない」
「牛の糞? 馬の小便? そんなの家来に飲み食いさせればいいじゃないの」
「また非道いことを云う。だからお前は――」
「なによ」
「――なんでもない。好きにしなさい」
婆もまた旅に出た。ただし爺とは違い、屈強な従者たち――牛糞係や馬尿係、彼らの監視役など――を連れてであった。爺の言葉通り、道に迷った辺りで牛方に出会った。牛の糞を突き出された。
「ヘラクレス、お食べ」と婆が命じる。従者の名前は仮称である。
婆の命に背けば格上のティタン(念のためだがこれも仮称である)から、こてんぱんな目に遭わされかねない。ヘラクレスは情けなさに涙ぐみながら糞を食った。
牛方が示した方向には馬方がいて、すでに腹を括っていたペルセウスは、
「はいはい、ペガススの小便だと思えば」と、運ばれてきた尿を豪快に飲み干した。
彼らの献身のお蔭で婆はまんまと竹林へと辿り着き、そこに雀たちの姿を見つけた。彼女らは感涙にむせびこそせぬものの、婆を追い返すことなく爺と同様にもてなした。従者たちも相伴にあずかった。「人の飯は美味い」とヘラクレスは泣いた。「おつゆが美味い」とペルセウスも泣いた。
翌朝、戸口で待機していた彼らの前に、婆は古ぼけた葛籠を背負って現れた。
「ああ、この重量感」とうっとりした顔付きでいる。「爺のときと違って奮発したもんだ」
運ぶのを手伝おうとする従者たちの手を、婆は払って、
「これはお守りです。お前たちに持たせて、お前たちがずんずん先に行ってしまって、私が道に迷ったらどうすんの」
婆に与えられた葛籠は、昨年、爺が試しに抱えてみた羽根切り雀の葛籠に相違なかった。実は中身も変わっていない。ではなぜ重かったのだろう?
爺と違い、婆は往路に於いて異界の禊【みそぎ】を経ていない。従者任せだった。よって「荷が重い」のである。彼女は勘違いしているが、重いのは中身ではなく葛籠そのものだ。
どうせ誰しもが知っているから結末を書いてしまうが、葛籠からは妖怪変化が飛び出してくる――芳年描くところによれば、三つ目のろくろ首や河童や一つ目の獣人や蛞蝓みたいなのや正体不明のすばしっこそうな奴らが。行儀よく詰合せになっていたはずがない。そんなに重い葛籠を背負えるわけがない。地べたに下ろされ蓋を開けられた、つまり雀の一族から課された役目を蔑ろにされた葛籠が怒り、一瞬にして愚連隊を呼び寄せたと解釈すべきであろう。葛籠自身が妖怪なのだ。それが証拠に芳年は葛籠に眼を描き表情を与えている。
そもそも妖怪変化というのは、自然物や道具が思念を獲得した状態に他ならない。丁重にされれば人々を守り、ぞんざいにされれば祟る。羽根切り雀に復讐心はなかった。葛籠の威力は本来婆に向かうものではなく彼女を加護するものだったし、中に入っていたのは戦死者たちへの「祈り」だった。婆が葛籠の重さに耐え、郷に帰ってからも入っていた反物を丁重に扱えば、爺に与えられた種子と同様、奇蹟を起こして人々に報いていたかもしれない。
しかし愚かな人はとことん愚かなもので、「覗かず、持ち帰る」という単純な約束が婆には守れなかった。葛籠を捨てて中身だけ運べば、すこしは軽くなる、楽ができるとでも思ったのだろう。雀たちの親切を等閑に、竹林すら出ていない時点で葛籠を下ろして開けた彼女は――。
再び芳年の筆に注目してみよう。妖怪たちより、それに驚きひっくり返っている婆のほうがよほどグロテスクで、正視に耐えない。よくもまあ人間をここまで醜く描けたものだと感心させられる。むろん描かれているのは彼女の本性である。着物の裏地が浅葱色だ。歌舞伎のルールでこの色は死を意味する。子供向けの版では婆が反省して終わったりするが、本当の「舌切り雀」はそんなに甘い話ではない。
婆は断末摩の悲鳴をあげながら、更なる異界へと引きずり込まれていった。永遠の地獄巡りが始まるのだ。古い葛籠と、中の反物と手紙だけが残った。従者たちは立ち尽くしている。
「なんか今、凄えもん見た」ようやっとヘラクレスが口を開くと、
「ああ。さすが芳年、妖怪どもが可愛く見えたもんな」とペルセウスもその意図するところを察して同意した。
「お前が退治したメドゥサってあんな感じ?」
「とんでもない。いくら髪の毛が蛇ったって、ユマ・サーマンが演じたくらいだぜ」
「悪くねえな」
「さっきの光景のほうが、よっぽど身が石になりそうだった」
「あんな化け物に仕えてて牛の糞まで食ったと思うと、情けねえや。田舎に帰りたくなってきた……ていうか、なんで俺たち、こんな国にいるんだっけ」
「背景と合ってないよな」
「希臘【ギリシャ】はどっちだろう」と無口なティタンが久々に声を発した。