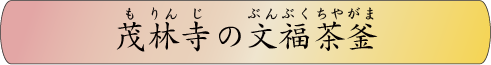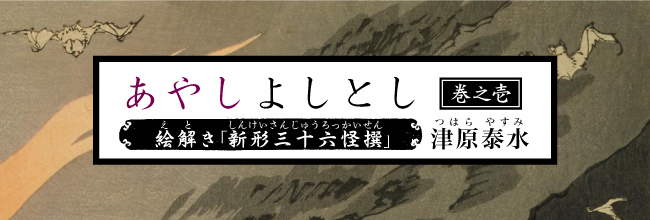子供の頃、童話「ぶんぶく茶釜」に接した人は多かろう。物語の内容は朧でも、茶釜に頭と四肢と尻尾が生えた、まるで狸と亀の合の子のような生き物が綱渡りをしている愉快な絵には、きっと見覚えをお持ちかと思う。徳川時代に流行ったあの傑作な図こそ「ぶんぶく茶釜」の本質であって、話の前後は付け足しに過ぎない。はっきり云って「鶴の恩返し」の狸版だ。ちなみに綱の上の狸がよく傘を差しているのはバランスをとるためだ。西洋の綱渡りは棒を持つが、日本では傘を持つ。
一夜、作家で云えば津原某に似た風情の、食うや食わずにして寂しい男の住処に狸がやって来て、これから茶釜に化けますから売ってお金に換えなさいと云う。また唐突な。そしてなんとなく失礼な。そもそもなんで狸が喋っているのだ?
「鶴の恩返し」で訪ねてくるのは美しい娘であって、爺さんだったか若者だったかが開けてはならない障子を開けてしまう瞬間がエロティックかつスリリングなのであって、最初から獣の姿で訪ねてくるんでは先の盛り上げようがないではないかと呆れつつ、
「やや、お前は先日、罠に掛かってじたばたしているのを、つい仏心から救ってやった――」と驚いてやる。
「そうなんですよ。あの老いぼれ狸でございます」
「そう流暢に人語を話せるんだったら、若い娘の姿で訪れてやろうといった配慮はできなかったのかね」
「すみません、思い付きませんでした。なんなら今から」
「いい、いい。化けてみたところで狸顔の醜女がせいぜいだろう。で、なんで茶釜?」
「贅沢品の象徴ってことで。なにせ茶の湯の道具ですから」
「しかし、この界隈で茶の湯を嗜むような風流人といったら……茂林寺の住持くらいか」
「えっ、あの寺は現存するんですか」
「足利時代から続く由緒ある寺が、そう簡単に潰れるものか。お前はこの辺の狸じゃないのか」
「昔は住んでたんでございますが、しばらく天竺に戻っておりまして。久々に支那を経由し海を渡ってきて懐かしい土地に足を踏み入れましたところ、寄る年波ゆえの白内障につき、まんまと猟師の罠に掛かってしまいました」
「天竺の狸なのか」
「はい。ですから梵語も話せます」
「なんと。しかし狸がどうやって大陸と日本を行き来するんだ」
「大概は荷物のふりを致します。行きたい先を記した紙を木箱に貼り付け、中に潜り込んでおくのがいちばん楽ですな。この辺からですと、まずは長崎、支那、そして天竺の寺へと勝手に運んでもらえます。長いときは何年も眠り続けねばなりませんが」
「お前、あんがい凄い狸なんだな。やっぱり今からでも女に化けてもらおうか」
「宜しい」と狸、梵語と思しき何やらを唱えはじめた。
やがて全身から閃光を発し……なら絵にも文章にも成りやすかろうけれど、うねうねと不器用な変身ぶりである。だんだん背が伸びてきて男と同じくらいの丈となり、顔面や四肢の毛は縮み、ほかの毛は逆に伸び、肩から下は艶やかな布に変じてその身を包んで、次第に女人の体【てい】を成してきた。
肌の浅黒さにさえ目を瞑れば、どうして、大層な美女に仕上がりはじめた。莞爾として男に話しかけてきたので、ここいらが完成形だろう。見た目は申し分ない。ただ――。
「おい狸、ちょっと狸、狸に戻って返事しろ」
女人は縮んで狸の姿へと戻り、「なにか問題が?」
「天竺の女ではないか。言葉が通じない」
「やはり大和撫子がご所望ですか。生憎と私、こちらではもっぱら僧のふりをし女色を避けておりましたんで、日本の女の仕組みがよく分かりません」
「エキゾチックな女が厭とは云わんが、言葉を交わせないではやる瀬ない。こう見えてもロマンチストなのだ。かといって坊主に変身されても法事のようで居心地が悪い。狸のままでいい。それにしても狸というのは、みなお前のように化けるものなのか」
「百歳や二百歳の仔狸には無理な相談ですな。つまり大概の狸は幻術を会得するまえに死んでしまいます」
「お前、いったい何歳なんだ?」
「かれこれ、二千と二百歳ほどになりましょうか」
男、唖然として、「また長く生きたな」
「仔狸の頃、お釈迦さまに頭を撫でていただからでしょうか。ご入滅の折にもじっと傍らに踞っておりました」
「なんと。すると日本の古い出来事もずいぶん眺めてきたことだろう」
「源平合戦はよく憶えております。来日するなり各地赤旗白旗の激戦だらけで、それはもう驚きました」
「茶釜にするには勿体ない狸だな。いっそ寺か塾でも開いたらどうだ」
「実はですね」と狸は浮かぬ表情で、「さっき話題に出ました茂林寺、あの開山のきっかけをつくったのは私でして――」
「ぶんぶく茶釜」の元となった説話は、肥前国平戸藩の藩主、松浦清(静山)による『甲子夜話【かっしやわ】』に「茂林寺の釜」として見られる。心形刀流【しんぎょうとうりゅう】の達人でもあったこの人物、遥か未来を見通していたかのような天才的文人でもあり、彼の蒐集により後世に残った絵画や大衆文学は数限りない。老いてのち天寿を全うするまでの二十年間に書かれた『甲子夜話』は、時事、風俗、海外事情から伝説伝承に至るまでなんでもござれの多彩な随想集で、なんと正編百巻、続編百巻、三編七十八巻にも及ぶ。日本が世界に誇るべき大エッセイストである。
芳年の「茂林寺の文福茶釜」には、一般に知られていた綱渡りの芸で貧しい男を稼がせる茶釜狸ではなく、「茂林寺の釜」の高僧の正体が描かれている。上州茂林寺は、諸国を行脚していた大林正通禅師が伊香保山麓で守鶴【しゅかく】なる僧と出会い意気投合、その勧めに応じて応永三三(一四二六)年、館林の地に結んだ庵がその始まりとされる。守鶴は代々の住持に仕えた。登場した時点ですでに老僧と記録されている彼だが、壮年の風貌を保っており、しかもそれ以上老けない。住持が老いて死に、入れ替わり、それが何代目になろうとも守鶴の風貌は変わらない。
彼が文字通り尻尾を出したのは、天正一五(一五八七)年。老僧として表舞台に登場してから既に百六十年余りが経過しているわけで、それまで妖怪扱いされていなかったことが寧ろ不思議なのであるが、十代住持天南青正が、とうとう居眠りしている彼の尻尾を目にしてしまう。それ以前もおかしなことがあるにはあった。元亀元(一五七〇)年の千人法会の際、ふるまいのための茶釜は守鶴が用意した。奇怪なるかなこの茶釜、汲んでも汲んでも湯が減らない。これは法力か、それとも魑魅魍魎のまやかしか? それ以前に守鶴の年齢が取り沙汰されなかったことがやっぱり不思議なのであるが、それだけ生きれば大概の人間に尻尾くらい生えようとも思うのであるが、尻尾の目撃によりようやっと「やはり妖怪変化であったか」「見られたか」というコンセンサスが成立したらしい。
「寺からの去り際、幻術の限りを尽くして、釈迦尊ご入滅のさまや源平合戦屋島の戦いを大パノラマで披露しておきました。そんじょそこらの悪戯狸と一緒にされるのは御免ですからね。それにしても、こうして喋っていたらだんだん腹が立ってきました。なんで尻尾が出ていたくらいであんな大事になっちゃったんでしょう。十代も真面目に仕えてたんですよ」
「狸の茶を飲まされ続けていたというのが、なんだか悔しかったのかもしれないな」
「狸差別だ。やっぱり茂林寺に復讐しましょう。茶釜に変身しますから今の住持に売ってください」
「二千歳を超える古狸にしては狭量だな。だいいち今の住持はなんの関係もないじゃないか。なんだったら法会のときの湯が絶えない茶釜をまた出してきて、それを見世物にでもして一儲けしたほうが手っ取り早くないか? 俺への恩返しにしても」
「なんであんな高度な分身が可能だったのか、今となっては分かりません。きっとお釈迦さまのご加護による奇蹟。それを見世物にして守鶴の名を汚せと」
「難しい奴だな。くだくだと喋っていたら腹が減るし行灯の油が勿体ないから、俺はもう寝るよ」
「あのう、私も上がらせていただいても――」
「勝手にしろ。物は盗むなよ。盗みたい物も無かろうが」
男は散らかった部屋に戻って灯りを落とし、煎餅布団にくるまった。
翌朝、目覚めてみると上がり框に茶釜があった。赤錆だらけだが拵えに風格がある。あるような気がする。本当は茶の湯になんぞ無縁だからさっぱり分からない。
「おい守鶴」と呼びかけてみたものの返事はない。
ゆうべの狸とのやり取りは、はて現実だったのだろうか。なにかの勢いで捨てられていた茶釜を抱えて運び込んでしまい、これが罠に掛かっていたあの狸だったらなどと、愉快な夢をみていただけではなかろうか。
もともと茶釜に過ぎないのなら風流人しか用はなく、守鶴が化け続けているなら本人の希望なのだから、けっきょく茂林寺に持ち込むほかない。運んでいって住持に見てもらった。住持、最初は茶釜の汚さに眉をひそめていたが、
「どうやらこちらに縁【ゆかり】のある品らしく、元亀元年の法会で――」
と男が疎覚えの説明を始めると、急に身を乗り出してきた。
「失礼ながら無学な貧乏人とお見受けしますが」
「本当に失礼ですな」
「いったいどちらで、かの千人法会の逸話を」
「こう云うとジャンキー扱いされそうですが、茶釜が教えてくれました」
「茶釜が喋った?」
「やや説明不足ながら、大雑把に云えばそういうことに。梵語も喋ります」
「むむ――守鶴さまが起こされた奇跡の数々は、この寺代々の語り種となっております。しかし私たちもジャンキー扱いされたくないので対外的には黙っておりました。するとこれが、かの紫金銅分福茶釜。赤錆まで有り難く見えてまいりました」
「それが正式名称なんですか」
「文【ふみ】に福と記していた住持もおりますが、近年は、福を分ける、を正式表記としております」
価値の程は即座には判断しようがないということで、とりあえず手付の金を握らされ、男は寺を後にした。これでしばらく食べるには困らないが、住持を騙してしまったような気がするし、べつに小金が欲しくて狸を助けたわけでもない。あのあと同じ罠に別の狸が掛かったかもしれない。もどかしい思いを抱えたまま、帰途、久々に腹一杯の飯を食べた。
夕刻、寺の者が荷物を抱えて男の住処を訪れた。謝礼の品かと思いきや、風呂敷が解かれてみれば寺に置いてきたあの錆び茶釜である。
男はおっかなびっくり、「なにか問題でも」
使いの僧は申し訳なさそうに、「入れても入れても水が増えない、さすが伝説の茶釜、と初め住持は喜んでいたのですが、なんのことはない底に穴が開いておりました。手付はそのままで結構ですから、茂林寺が買い取ろうとしたことは口外しないでいただきたい、とのこと」
「やっぱり不良品でしたか。すみません、茶釜が茂林寺に売れと云うもんだから――」
またジャンキー扱いされかねない発言を重ねてしまったと気付き、口を噤んで視線を泳がせている男に、
「私はそれ、本物の分福茶釜だと思いますよ。もう茶釜としては役立たずですけど」と若い僧は告げ、一礼をして去っていった。
男の住処はまた静かになった。彼は錆び茶釜を撫でながら、「守鶴、もう狸に戻っていいぞ。なんなら天竺の女でもいい」
しかし茶釜は茶釜のままである。
「意地を張るか」と男は笑った。「火に掛けられて火傷をし、頭や尻尾を出して亀みたいな姿ででも逃げ帰ってくれば、黄表紙のようで面白いとさっき空想していたが、まさかそのまま突き返されてこようとはな。守鶴、お前は狸が茶釜に化けているのか、それとも茶釜が狸に化けていたのか?」
日が暮れていく。男は茶釜を撫でては言葉をかけ続けた。
「なあ守鶴、機嫌がいいなら聞かせてくれ。こんな俺だって教養は欲しいんだ。俺たちが拝んでいるお釈迦さまというのはいったい――」
ひもじくも寂しくもない夜を迎えるのは、本当に久し振りだった。