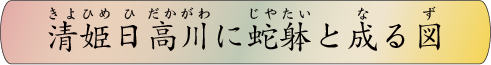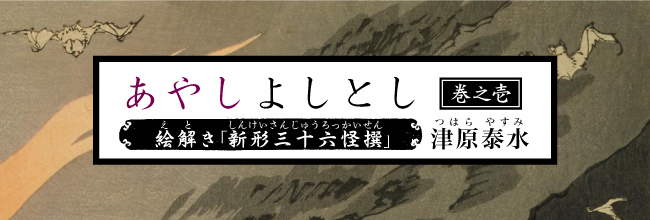『三十六怪撰』のなかでも出色の一葉だ。
僧安珍と荘官の娘清姫の伝説は、道成寺とも日高川とも題され、能、浄瑠璃、歌舞伎といったさまざまな芸能で表されてきた。
延長六(西暦九二八)年の話だというから古い。都は平安京、未だ平将門の乱も起きていない。のちの大陰陽師安倍晴明は六、七歳の少年である。母親が狐であることにそろそろ気付いた頃か。
清明の話は「葛の葉」の項に譲って、今は芳年が描いたこの清姫を語ろう。衣類が時代背景と合っていないのは、明治の歌舞伎を反映しているからだ。歌舞伎というのは伝統的に時代考証に大らかで。十年も百年も「大雑把に昔」といったところがある。その慣習を逆用して時事ネタを「昔の話でございます」と称して上演したりもする。
襦袢の赤が鮮やかだ。歌舞伎には、赤色を纏った人は真意を見せているという暗黙のルールがある。いかに突飛な告白であってもその話者が赤い褌でも覗かせていたなら、それは芝居のなかの「真実」なのだ。
この清姫の真実は、ハンサムな安珍への恋情――それはそれは凄まじい片想いである。古今東西に類を見ない極めつけの執念でもって、たったいま彼女は日高川の急流を渡ってきた。いったいどこにそんな能力を秘めていたものか、狂おしい想いから大蛇に変身までして。
鱗文【うろこもん】と呼ばれる三角形を組み合わせた着物の柄、長く引きずられた蓬色の帯は、彼女が客観的にはもはや大蛇でしかないことの象徴だ。そして物語はそれだけではない。よりによってあんな場所で死を遂げようとは、この時点での安珍は予想だにしていない。
ちらちらと熱い視線を送られていることに気付いてはいたが、夜這いをかけられたのにはさすがに驚いた。修験の道を究めんと、奧州から遙々、この熊野の地を目指してきた。その巡礼の最中である。しかも相手は大富豪の一人娘。指一本でも触れた日には、仏罰神罰人罰がまとめて押し寄せてきかねない。
「せめてキスだけ。いいじゃない、減るもんじゃなし」と、先刻安珍が火を入れた行灯に頬を照らされた娘が、目を閉じる。
「それ、本当に無理なんで」と安珍は床に手を付き頭をさげた。「私にも人生設計とかありますんで、ここはひとつ」
清姫は紅をさした唇を尖らせ、「ねえ、もう修業とか辞めちゃって、この家の婿に来れば? いいよ、私」
「泊めてもらった全員にそう云ってんじゃないでしょうね」
「失礼な。現実の男性に興味を持つのなんて、生まれて初めてですって。証拠見る? 脱ぐ?」
「滅相もない。そもそも私なんかのどこがそんなに――」
「顔」
あっさりと云ってのけた清姫を上目に、安珍は思った。野宿すればよかった。
元来、女嫌いではない。昔は色々とやらかしたうえで、それを悔いての出家だった。ここで変節したとて、庄司の婿といったら左団扇を保証されるようなものだし、この清姫がまた困ったことに醜女ではない。というか、かなり可愛い。いや、そうとう可愛い。
だが、いっそ破戒か食い逃げかといった気持ちが、ふしぎと一向に湧かない。あどけなさすら残した良家の秘蔵っ娘のくせして、あばずれめいた危険な匂いがぷんぷんするのである。そもそも初対面のその晩に夜這いをかけてくるか?
「こうしよう。今は参詣中だから身をきれいに保たなきゃいけないんだけど、終わったら帰りに寄るよ」
「絶対?」
「うん」
「そのときキスしてくれる?」
無言で頷くにとどめた。もはや頭のなかではこの館を避けての復路を計画しはじめていた。
清姫の父・真砂の庄司の館には、数多くの参詣者たちが宿を求めていた。館は紀伊路の一部をなす中辺路【なかへち】にあったとされる。いわゆる熊野古道の一つだ。
奧州の人である安珍が、なぜこの館に泊まったのか。東からの旅人ならば伊勢で進路を南にとり、熊野灘側(紀伊半島の東岸)から熊野三山へと分け入るほうが合理的に見える。しかしいったん京を経て、西岸を南下したあと山中を抜ける紀伊路こそ、修業に相応しい正式ルートとされていた。紀伊半島をほぼ横断、往復するわけだ。
起伏に満ち、たびたび溪流に行く手を阻まれ、熊も猪も狼も出る険しい道のりだ。下手をすれば命を落とす。それぞれの社に辿り着いてからも柏手を打って終わりではない。二日も三日も祈祷を続けて、権現から霊力を授かるのである。
安珍との約束を真に受けている清姫は、彼の旅の安全を祈りつつ、再会の日を指折り数えて待っている。しかしほかの参詣者たちはとうに戻っているのに、彼はなかなか姿を現さない。昨日も来ない。今日も来ない。
焦れるがあまり道端に立ち、往還する人々に安珍の衣の色を教えては、見掛けなかったかと尋ねはじめた。
一人の僧が記憶していた。「そいつ、もしかして市川雷蔵ばりのハンサムじゃない?」
「そうそう、眠狂四郎っぽいの」
「だったら那智で一緒になったよ。もう満願成就って云ってたから、二、三日前にはこの辺を通ってんじゃないかな」
素通りされた! 清姫は激情のあまり裸足で駆け出す――。
『今昔物語集』に所収された説話では、清姫に該当する女はこの時点で寝所に籠もり、そのまま死んでしまうのである。やがてそこから五尋(一尋は両手を左右に広げた指先から指先まで。すなわち七メートル半から八メートル)の毒蛇が出てくる。
もちろんここでは芳年も描いている、生身のまま安珍を追う清姫のほうを描いていく。
生身とはいえ、怒りに歪んだかんばせを屈辱の涙で濡らし、着衣の乱れも意に介さず、呪詛めいた言葉を吐き散らしながら山道を猛然と駆けてゆく清姫の姿は、もはや鬼女である。
旅人を見つけては追い縋り、私の安珍を知らない? 安珍さまを見なかった? と問い詰める。大概の者は気味悪がって逃げていくが、ときには親切な者もいて、その狂乱ぶりを哀れみ、
「人捜しかい」と、要領をえない彼女の言葉に耳を傾け、目撃していればその場所を教えてくれた。安珍の美貌はなにしろ目立つ。
当の安珍、近くの里にて過酷な参詣で疲れきった身を休めたのち、また旅の支度を調えたところである。各地の寺社に宿を求めながら、また京へと上っていく心算だ。
出立の路上で、
「安珍さま!」という金切り声に呼び止められた。
振り返り見て、愕然となった。山姥ばりの着崩れの裾から血まみれの足を覗かせた女が、黒髪を乱してこちらに迫ってくる。清姫に似た貌立ちの狂女かと思ったが、自分を知っているのだから恐らく本人である。
立ち竦んでいる安珍の胸ぐらを引っ掴まえ、喚きちらしているその言葉は、半分も聞き取れない。自分とすでに夫婦の契りを交わしたものと思い違っているらしいとだけ、かろうじて分かった。
「人違いですよ」
とその手を引き剥がさんとすると、いっそう激昂してしがみついてきた。この力がとても人間とは思えない。時代が時代であれば、火事場の女がピアノを運び出してしまったというエピソードが思い起こされたであろう、凄まじい怪力である。
これは間違いなく殺されると感じた安珍、咄嗟に修験者の守り神に祈りを捧げる。「南無金剛童子、助け給え」
熊野参詣を経ていたがゆえの霊験か、はたまた単なる偶然か、ふと清姫の力が緩んで、その身が地面にひっくり返った。虚空を見つめ、あうあうと口を動かすばかりで、身じろぎできずにいる。金縛りだ。
やっと金縛りが解けた清姫、起き上がって辺りを見回すものの、当然のごとく安珍の姿はない。彼が歩み出そうとしていた方角を思い返し、そちらに向かってまた全力で駆け出す。
もはや心は空っぽに近い。安珍を追うことそのものが、奇怪な苦行とさえ化している。足の感覚はすっかり麻痺して、宙を滑っているかのようだ。
やがて日高川が、清姫の行く手を阻む。たびたび周辺地域に水害をもたらしてきた急流である。橋もない。
渡し場を目にした彼女、安珍は船で渡って道成寺に向かったようだと、その薄れた理性で推し量る。女人禁制の寺に匿ってもらうつもりなのだと。
渡し守への呼掛けは、まともな人語を成していただろうか? 夫に追い着きたいのです、今はただ追い着ければいいのです、と懸命に主張してはみたものの、犬畜生のように追い払われてしまった。金を貰った以上はどうのと云っていたけれど、はて私は金子など持っていたかしら。それとも安珍さまが払った渡し賃の話かしら。
そんなことより一刻も早く彼の側に行かないと。だって妻ですもの。それからどうするんだったかしら。走っているあいだにドーパミンが出過ぎて忘れてしまった。
あ、思い出した。キスしてもらうの。
川の向こうで、ぎゅっと安珍さまを抱き締めて、私はキスをしてもらうの。
急がなきゃ、と清姫は、ためらいもなく日高川の流れへと、血まみれの足を踏み入れる――。
幾重もの着物や帯を纏った小娘と、急流との間に生まれる抗力はいかばかりか? 基本的に抗力は、物体と流体との相対速度の二乗に比例する。単純に云い換えれば、ゆるゆる流れる下流とその倍の速度がある上流とでは、勢いに四倍の差があるということだ。藻掻いて水面に顔を出せば、ここに造波抵抗というものがまた生じる。まあそうなる以前に、着物が大量の空気を含んでいるから身を沈めて水を掻くことができない。浮かんだままで流されていくほかない。結論として、着物姿の箱入り娘は速い川を泳げない。
それでもなぜか対岸へと渡りきってしまった清姫に、自分がいつしか異形の存在に変じているという自覚はない。本人は恋に恋する乙女のままの心地でいる。その瞬間を捉えたのが、「清姫日高川に蛇躰と成る図」だ。
むしろ客観的だったのは、道成寺への参道を這い上ってくる大蛇の鱗の輝きを遠目にした、安珍のほうだ。
「今のぎらって光、あれ清姫ですよ。ぜったい清姫だ。わあ来る。もう来る」
とパニックに陥っている美男子に、僧たちは、
「その女がたとえ魑魅魍魎になり果てていても、俺たちが退散の祈祷でなんとかするから」
と懸命に云い含め、
「お前のためならな」
とウィンクを送り、当座の食料など持たせて、境内の梵鐘の下に坐らせる。そして力を合わせて鐘を地面まで下ろし、彼を隠す。仏に加護された鉄のシェルターである。
平然と境内まで上がってきた大蛇の姿には、さすがに寺じゅうが腰を抜かしたが、蛇のほうはほかの僧たちに目もくれず、まっすぐ鐘へと這い寄って、固く巻きつく――抱き締める。
多くの場合、ここで大蛇が火を吐いて安珍を焼き殺した、もしくは蒸し殺したと語られるのだが、その展開には少々違和感をおぼえる。古来各国に於いて、長く冷たく塒【とぐろ】をも巻く蛇は水の象徴であって、清姫が日高川を渡れたのも、水そのものに変化したからに違いない。それが急に対極のエレメントである火を吐くのは不自然だ。海千山千(海に千年、山に千年棲めば、蛇も龍に変わるとの伝え)で、森羅万象を統べる存在へと登りつめたわけでもない。よって本稿は異説の立場をとり、以下のように物語を締め括る。
大蛇は、幾日経っても道成寺の釣り鐘に巻きついたままである。僧たちは恐ろしくて近付けないが、ただ鐘に巻きついているだけで、ほかに危害を加えるわけではない。
ある朝、僧の一人が、大蛇が梵鐘から離れていく瞬間を目撃する。おっかなびっくり後を追ってみて、その輝きが参道を下り日高川に向かうのを確認する。
輝きは川の流れと一体となり、下流へと消えた。
寺に戻ってきた彼の報告を聞いた住持は、急いで鐘を上げさせる。なかで安珍は、綺麗な顔のまま息絶えていた。窒息であろう。まだ温かかった。
ついさっき死んだらしい。