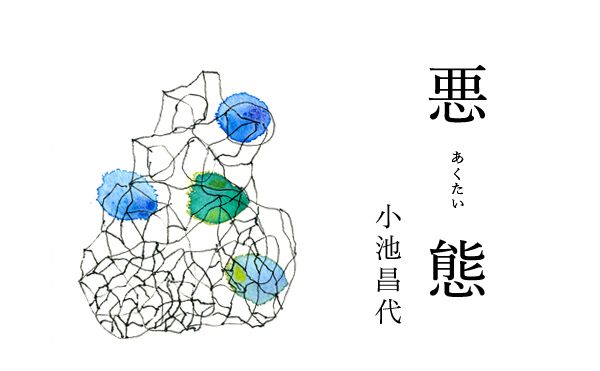ほこりのまざった街の匂いがした。ひんやりとした空気が首のまわりをマフラーのように囲んだ。黒い猫が路地から出てきて、タイボクをじろりと眺め、停まっていた車の下へ、するりともぐりこんで姿を消した。
タイボクは一人だった。しかし自由だった。
ある程度のお金さえあれば、こうして一人でも生きていけるんじゃないか。タイボクはそんなことをいきなり思ったのだった。
父もいない、母もいない。それはさびしい、そしてふあんだ。同時に、とてつもなくはればれとする。そんな初めての感情に、タイボクは一瞬、戸惑った。
大阪にだって、九州にだって、この足でこのままふらりと行くことができる。お金さえあれば。鳥みたいに。
そのお金を稼ぐ手段は今のところなかったし、具体的にどうしたらよいのかが見えなかったが、金が流れている世間のごく近くを、今の自分は歩いていると思った。
とにかくその道を見つけるまでは、「父の子供」でいるしかない。地面をにらみながら歩いていると、タイボクくん!と呼ぶ人がいる。
京平のお母さんだ。
いつも化粧っ気がなく、忙しそうにしている。実際、京平のお母さんは忙しい。少し離れた街にあるお菓子の工場で働いている。
いつか、形の崩れたケーキをたくさんもらった。市場に出せない不良品は、従業員が自由に持ち帰っていいそうなのだ。
そのとき、京平のお母さんが働いているということを初めて知った。京平はちょっと恥ずかしそうだったが、タイボクは、こんなにおいしいケーキが、ただで貰えるという職場がうらやましくてならなかった。
友だちのお母さんのすべてが働いているわけではなかった。子供たちの間でも、専業主婦という言葉は定着していて、だれそれのお母さんはセンギョーだなどと省略形で言う。でもオトナたちは、自分たちがそのように呼ばれていることをまるで知らない。
働いているお母さんのなかには、いきいき、きびきびとした人もいれば、いかにも余裕がなく疲れている人もいた。スーツみたいなのを着ている人もいれば、普段着で働きに行っている京平のお母さんのような人もいた。
そのお母さんがくれたというのは、レモンの匂いのするレモンケーキだ。割れていたり、こげたりしていたけど、まっとうに焼きあがったものは、小袋につめられ、さらに箱につめられてデパートでも売られているらしい。
あんまりおいしかったので、学校でレモンケーキのことを京平に言った。ああ、あれね、もう食べ飽きたと、京平は言った。タイボクは言葉がなかった。くれと言いたかったが、言えなかった。以来、このお母さんを見ると、咄嗟にレモンケーキが思い浮かぶ。そういえば、最近、貰っていない。
「タイボクくん、福包の餃子、食べてきたの?」
「うん」
「今夜、お父さんが遅いんだね」
「はい」
「心細かったから、うちに来ていいよ」
「だいじょうぶです」
「困ったことがあったら、電話するんだよ」
「はい」
「京平はいま、山田先生のとこに行ってるの」
「あ、京平から聞きました……なんだか面白そうな塾……。あ、おれ、受験しませんけど」
「受験塾と少し違うのよ、タイボクくん、作文うまいからなぁ」
「そんなことないです」
「だから、山田先生のとこ、行くと面白いんじゃないかなって、京平と話してたの」
「そうですか」
「体験もあるからおいでよ」
「体験って?」
「体験授業だよ。ただで受けられるよ。やってみて、面白そうなら、お父さんに頼んでみればいいじゃない」
「はい」
問題は授業料だが、目の前の人に、いきなりは聞けない。
「それじゃ、また、遊びにおいでね!」
京平のお母さんは、寒がりなのか、ダウンコートを着て、すっかり冬のような出で立ちだ。タイボクの母親とは仲が良かった人なので、タイボクにも親しみがある。そばかすだらけの素顔を、おしげもなくさらけだしているこの人を、京平はちょっと恥ずかしく思っているようだった。いつかの保護者会のとき、京平が、おかあさーん、化粧くらいしてよと、小さい声で言うのをタイボクは聞き逃さなかった。
なんだか無性に「ママ」が懐かしかった。今頃何をしているんだろう。
→10へ続く