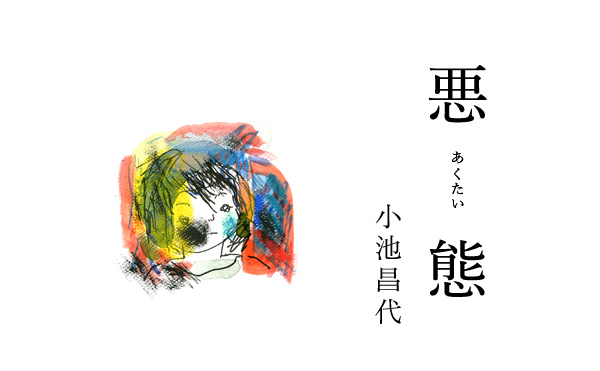母親がいたときは、何の問題もなかった。むしろ怖い父親など、出かけてくれたほうがよかったくらいだ。
「パパ、今夜仕事で遅くなるらしいよ、日曜日なのに、大変だね。タイボク、今夜、何食べようか?」
母の言い方には、いつだって二人の天国みたいなニュアンスがあった。
タイボクはたいてい、グラタンかハンバーグか餃子と言う。驚くことに、母はだめと言わない。このなかで一番、難しそうなのがグラタンだったが、おそるおそる「グラタン」とつぶやくと、母は粉チーズをたっぷりかけて、オーブンで手作りのグラタンを焼いてくれた。それは驚くほどうまかった。熱かったけど、グラタン皿にこびりついた焦げチーズをがりがりはがし、なめるように食べた。
父と二人で暮らすようになってからは、もちろん、それは夢と消えた。だいたい、父は洋食を好まない。父が好きなのは、茶色っぽい食べ物か白っぽい食べ物で、茶色の代表は煮物か佃煮。白の代表は豆腐である。
「グラタン」と心のなかでつぶやくだけで、ほとんど泣きたいような気持ちになる。いつかきっと自分で作ってみたい。その日はそんなに遠くないと思う。学校の家庭科の授業ではカレーライスを作った。市販のルーなんか、使わない。カレーパウダーから作ったんだ。タイボクはそのとき、手応えを感じた。この「手」を使って努力すれば、人生を必ず切り開いていけるという、そういう感触の、ほんの端っこを掴んだのだった。
ある日曜日。今日くらいは大丈夫だろうって思っていると、父の携帯がぶるぶると振動した。
「あ、了解です」
父はそう言って、スマホを切ったあと、一呼吸置いてから横を向き、誰にともなく「わるいな」と言った。
タイボクは日曜日に鳴る電話のベルが大嫌いだ。
父の着信音は虫の声。
「なんで?」と聞いたら、
「虫の声は、あんまり強制的じゃないだろ? 虫に呼び出されるなら、仕方がないかなあって思えるんだ」
父は笑って言ったが、タイボクはむしろ真顔になった。虫の声だろうと、誰の声だろうと、駆り出されるのは同じだから。
それでもむかしの電話に比べれば、虫の声は確かにやさしくて風流だ。父のお母さん、つまりタイボクにとってのおばあちゃんちの電話は、耳をつんざく轟音がする。けたたましいが、それでないと、おばあちゃんには聴こえないみたいだ。昭和の黒電話は権力者だ。おばあちゃんは、一人で名古屋に住んでいる。東京へ来なよ、タイボクもいるし俺も助かるし。父がそう言って誘ったことがあるのだが、おばあちゃんの返事は一言、「嫌だよ」。がんこなばばあだと、父は言った。
「これから、局へ行ってくるけど、タイボク、少しの間、一人でがんばってくれ。今からじゃ、夕食には戻れないかもしれない。……おそらくそうなる。午後五時の鐘が鳴るまでに連絡がなかったら、一人で、福包へ行って、餃子ライスを食べろ。早めにシャワーをあびて、明日の準備をしてから寝ろ」
タイボクは、分かった、と言う。それしか言うことはない。
タイボクの町では、スピーカーから――確認したことはないので、それがいったい、どこに設置されてあるのか、わからないのだが――夕方五時になると、毎日、夕焼け小焼けのメロディーが流れる。結構大きなボリュームなので、タイボクはうるせーなーと思っている。でもそれが、ひとつの目安になっていることも確かなことで、小さい子供たちは、そわそわしだすし、もしかしたら、カラスなんかにも聴こえているんじゃないかと思う。五時を過ぎると、ねぐらに帰るカラスが一斉に鳴き始め、空が黒い翼で汚れる。かーかーかーという声は、「夕焼け小焼け」によく似合う。
秋から冬へと向かうこの季節、午後五時といえば、もう真っ暗だ。小学生を一人で歩かせたくはない。父がそう思っているのを、タイボクはよくわかっている。だからこそ逆に明るい声で言う。
「福包の餃子、食べていいの? やった、バンザイ」
「ああ、いいさ、二十個でも三十個でも」
「えっ、まじで」
「ああ、好きなだけ食べろ」
福包の餃子は驚くほど安い。子供が二十個、三十個、たとえ四十個食べようとも、親が破産するようなことはない。このあたりで、食べ盛りの子供におもいっきり食べさせてやれる店は、福包をおいて他にない。
キャベツがほとんどで、肉は探してもなかなか目につかないと悪口を言うひともいるが、タイボクは福包の餃子ライスを気に入っている。
「タイボクがうちの餃子を好きなのは、そりゃあもう、決まっていることなんだから」
福包のおばさんは、タイボクを見ると、それを言わないと気がすまないみたいに繰り返す。
「なにしろ、生まれる前から食べていたんだからね」
タイボクがお腹の中にいるときから、父と母は、よく福包で餃子ライスを食べたのだそうだ。その頃二人は、まだ仲がよかった。
→9へ続く