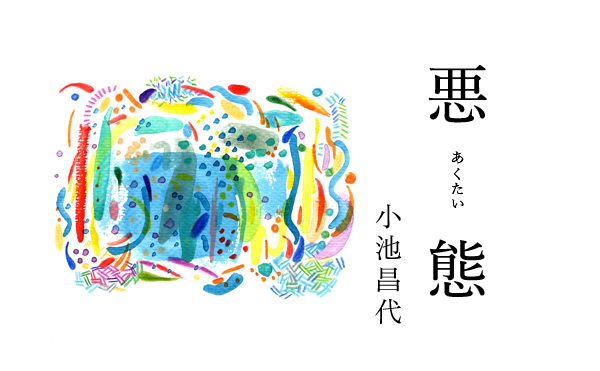タイボクの孫悟空は、多くの観客を惹きつけたが、本人もまだそのことは知らず、ただ舞台という空間に、不思議な魅力を覚えただけだった。
どんな子供にも、その子を取り巻く、その子だけの「空気」がある。舞台という板の上では、その微妙なものの差が、大きく歴然として見えてくるようなのだった。
タイボクの空気は光っていた。器用なせりふまわしとはとても言えなかったが、活き活きとした手足の動きは海老のようで、その命の弾みに、多くの人が目を見はった。
そうして注目を集める子の一方には、容易に見過ごされてしまう子供もいる。その意味で舞台は残酷な装置であると言えたが、見過ごされてしまう子だって舞台を降りれば、その子らしい、その子だけの光を発している。鋭い光、圧倒的な光、鈍い光、微弱な光。光の強弱が違うだけで、どんな子供も世界の光源だ。
最後の最後、みんなが舞台の袖に引っ込んだとき、同じクラスの花という女の子が、タイボクのそばに、つっと寄った。
「すごく、よかったよ」と花は言った。
花は「西遊記」では、道端に立つ、背景の桜の木の役だった。せりふはないし、ずっと立っているだけ。枝のかわりに手を伸ばし、最後、手のなかに握りしめていた桜の花びらを、ぱっと舞台に巻かなければならない。
タイボクが黙っていると、花は聞こえないのかというように、
「ほんと、よかったって、タイボク」と繰り返した。
それを耳にした連中から、ひゅーっとひやかしの声があがる。タイボクは照れて、怒ったような顔で花を睨みつけた。
花は、まあまあという感じで両手を上下させ、騒ぎ立てるみんなをなだめるような仕草をした。
花は頭がいい。タイボクはかなわない。中学受験で有名な最大手の塾、トータルワンに通っていて、そのなかでも成績がトップの人だけが集められているというSクラスに在籍している。すげえんだぜ、あいつ。受験組の連中から、タイボクも幾度か噂を聞いた。
でも花は、チビだし小太りだし決して可愛いというタイプではない。男子の人気は今ひとつだ。それにいつだって不敵な自信をその体から発散していて、タイボクは花を、小さな女政治家だと、ひそかに思っていた。
褒められるのは心底うれしいが、咄嗟に「ありがとう」などとは言えやしない。タイボクは、ひやかした連中に向かって、「やめろよ、てめーら」と言うのがせいぜいだった。
タイボクの母は、観客の一人として体育館の片隅に座っている。息子の活躍には胸が踊った。あの子、わたしの、わたしの一人息子なんです。暗闇のなかで隣の人に、そう、自慢したくなる気持ちだった。
声変わり前の声には、まだ子供らしさが残っていたが、それでも母は、そこに、たくましさとかすかな不安を聞き逃さなかった。
タイボクが三年生のとき、この母は家を出た。以来、母と息子は一度も会っていない。
六年生の演目が終わり、いま、場内は大きな拍手に包まれている。明かりがつく前に母は椅子から立ち上がり、誰よりも早く会場を後にする。
おそらくこれから校長先生の挨拶があって、子供たちは教室で解散となるだろう。
母は知った誰かに見つかる前に、この場を離れてしまいたかった。帽子を深くかぶり直し、腰をこごめて体育館の外へ出る。
昨日、タイボクの父から、メールが入った。「三人で飯を食おう」。それだけがぼそっと書いてあった。今日はその人も、忙しい仕事に区切りをつけて、タイボクの孫悟空を観に来ていたはずだ。彼はまだ会場のなかにいるだろう。
母はぼんやりした頭で、足の向く方向へ歩き出す。そのとき、サイレントにしておいたバッグのなかの携帯が、ぶるぶると激しく震えた。咄嗟に取り上げて、もしもしと言う。
「あ、おれ」
むかし夫だった人の声が、思いの外、明るく耳に飛び込んできた。
昔はその声におびえていた。機嫌がいいか悪いかが、すぐに声に出るひとで、しかもいいことはめったになく、いつも疲れて不機嫌だった。
「いま、どこにいる?」
「わたし、会場の外」
「なんだ、観てないの?」
「ううん、観たよ。タイボク、よかったね、とってもよかった」
「うん、うん、なかなかがんばってたな。おれもいま、出てきたところ」
タイボクの育て方をめぐっても喧嘩の絶えない夫婦だったが、さすがに今日は平和である。
「そっちへ行くよ、合流しよう」
「体育館を出てから駅のほうへまっすぐ歩いてきて。桜の木があったでしょ」
「ああ」
「その下にいるから。あ――」
「何?」
「わかるかな」
「そんなに変わったの」
「あたしのことじゃなくて。桜の木、あなたにわかるかしら?」
「桜だろ、知ってるよ」
「だって桜は、まだ咲いていないのよ」
< 「ああ、そうだけど」
「花がなくて、幹だけで」
「わかるさ。幹だけで」
「ふーん」
「バカにするなよ」
「バカになんてしてないわ」
「じゃあ、そこでな」
「ええ」
どうでもよいようなことを話しながら、ふと昔の時間が二人に蘇ってくる。
母は、桜の木で、かつてタイボクと待ち合わせをしたことを思い出す。ママァと叫びながら近づいてくる、小さなタイボク。
どうして父と母が別れなければならなかったのか。どうしてタイボクが父と暮らすことになったのか。
いつかはきちんと話さなければいけない。そう思いながら、今、母は桜の木の下に来て、足元の、盛り上がった根っこをじっと見つめていた。
→15へ続く