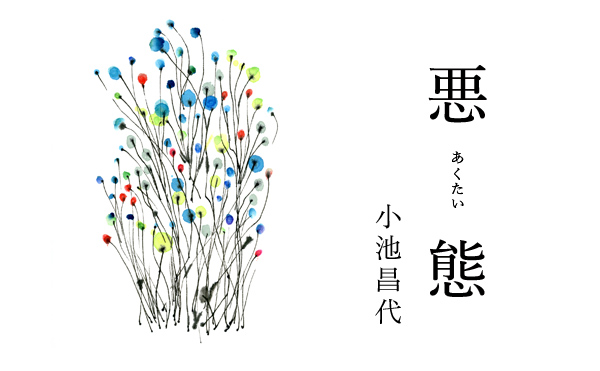そのなかにはタイボクもいた。
おーい、タイボク。清崎は呼びつけるようにタイボクを呼んだが、タイボクは返事もしないし、清崎のほうへ近寄りもしなかった。
「おまえってさ、女とばかり帰るな、女みてえ」
確かにタイボクの周りには、そのとき、女子ばかりがいた。誘ったわけではない。誘われたわけでもない。単なる偶然だ。
「おまえ、下手だなって京平が言ってたぞ。三人の孫悟空の中で一番下手だって。猿だからお面いらないって」
女子たちが、最後のところでわっと笑った。タイボクは裏切られたような気持ちになった。誰か一人くらいは、そんなことないよって言ってくれてもいいのに。そう思った自分は甘いなと思いながら、外履きの運動靴にかえ、じゃあな、と誰にともなく言い、走りかけたとき、清崎がタイボクの足に足をかけ、タイボクはつんのめりそうになりながら、おっとっとっと、すんでのところで、ころばずに持ち直した。
ばーか。
ばーのところにとりわけ力を込め、タイボクは清崎に叫ぶ。
清崎、何も言えずに、実に気持ちの悪い真顔で、タイボクをじーっと見た。
走り去るタイボクに女子たちも続いた。振り返ると、下駄箱のところに一人取り残された清崎が、やけに貧相で孤独に見える。あいつ、痩せてるなとタイボクは思った。
「京平が言っていた」というせりふが、胸にひっかかっていたが、直接それを聞いたわけではない。自分の目と耳以外は信用するなと、日頃から父に言われている。あんなチンピラに負けてたまるか。いじめられたらいじめかえしてやる。誰に教わったわけでもないのに、タイボクのなかには、そんな気持ちがむらむらとわきあがってきて、どうにもこうにも抑えようがない。
タイボクには妙な自信と自負があった。孫悟空のトリプルキャストで、他の二人と自分を比べたことはない、比べたことはないが、孫悟空をリレーのように三人で演じることが、どうにも歯がゆくてならなかった。
タイボクの演技について、面と向かって褒めてくれる人は一人としていなかったが、タイボクはどこかで確信していた。
自分こそが孫悟空だと。口に出していえば、どんなにいばって聞こえるか。それがわかるから決して言葉にはしなかったが、自分のなかにどしんと置かれた不思議な自信の感触に、タイボクは自分でも驚き、支えられていた。
京平に問いただしてみようとは、かすかにも思わなかった。
それよりも明日のキッズフェスタにやってくるというママのことが気がかりだった。ママと父さんは、どんな顔をして何を話すのか。
二人が夜中にやりあっている声を、以前、タイボクは聞いてしまったことがある。あんな声を出すママをタイボクは初めて知った。獣のようなうなり声だった。ママが狂ってしまったとそのとき思った。タイボクは声をあげた泣いた。すると二人は、ドアの向こうでぴたりと喧嘩をやめた。喧嘩は終わったというのに、二人はそのあと別れてしまった。
あのとき自分が泣いたから。
だから別れたのだと、タイボクはひそかに思っていた。
→14へ続く