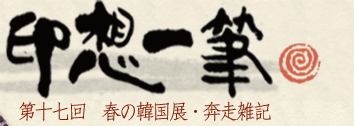※画像はクリックすると拡大画像を開きます。
「パンフレットに使うメインになる写真が欲しいなぁ…」そう思っていた矢先、いい話が舞い込んできた。自費出版本14集が朝日新聞の各関西版に載ったのだ。それを見たテレビ局が私を取材したいという。
さっそく送られてきた資料を見ると取材時間は5時間…。さらに聞くとオンエアーは2分間だそうだ。
1週間も経たないうちに撮影隊がやってきた。撮影は予定通り、5時間かかった。関西のテレビ局の若いディレクター「芸術家のものは時間をかけます」と熱っぽく語った。石印を並べ印墨画のパネルをバックに撮影が始まった。照明設備も設定も素晴らしく整っているので、個展用写真としても十分使える。「私にもここのカットを撮らせて下さい」と頼んでみた。テレビ局の人も快く了解してくれ、カメラマンが「私が撮ってあげましょう」と私のデジカメで撮ってくれた。
韓国展のメインの写真が撮れたのは大きな収穫だ。それから資料をそろえて翻訳者へ渡し、なんとか予定通り、2月末までに韓国へ送ることができた。
 さてこの後、ハングル語で描いた作品は、数点パンフレットに載せることにしているが少し遅くても大丈夫だという。だが、数枚といえどもハングル語で書くことが全く初めてである私が、いきなり本番だと心配なのか、翻訳の方が「一度見せてくれませんか?」という。 さてこの後、ハングル語で描いた作品は、数点パンフレットに載せることにしているが少し遅くても大丈夫だという。だが、数枚といえどもハングル語で書くことが全く初めてである私が、いきなり本番だと心配なのか、翻訳の方が「一度見せてくれませんか?」という。
これまで絵も文字もほとんど下書きなし、練習なしなので、見てもらうために書くのは初めてのこと。なかなかどうして、緊張するものだ。それと何でもそうだが、そのまま写すのと、理解して書くのとでは大きな違いがある。しかも、初めから“写す”つもりなどはなく、どのように“崩す”かを考えて書くのだから、翻訳の人の心配もよくわかる。
我々日本人が見るとあのハングルの文字は、文字というより記号のように思えるのではないだろうか。だがハングルで書かれた書道作品は、現代的な表現で素晴しいものだった。単純な記号を墨で並べているだけのようなのに、何ともいえない面白さを感じる。漢字のように意味を感じることもなく、わからないから尚更ストレートに良さが伝わってくるのだろうか。「いいなぁ、ハングルの文字も…」というその時の感動を覚えている。
朝早く起きて、作品にする翻訳文を墨で書いてみた。今まで墨といえば書にぶつかり、「漢字」「かな」となるのだが、こうして記号を書くのも楽しい。さて、どこまで崩して良いのかわからないが、そのわからないところもハングル表現の面白さだろう。さっそく翻訳の人に試し書きを見てもらい、細かい部分を指摘してもらった。だが「なかなか良いですね」とおだててくれたので、少し自信を持って次を書くことができた。
 さて書きながら「今回のような韓国展の話がなかったら、ハングル語など生涯書くこともなかっただろう」と感慨ひとしおだった。また初めての出会いから、いろいろな縁がこれほど広がってゆく不思議さを思うと、柳先生にはよくよく感謝しなければならない――そんなことを思いながら、「そうそう、梅見にも行く頃だな」と思うのだった。 さて書きながら「今回のような韓国展の話がなかったら、ハングル語など生涯書くこともなかっただろう」と感慨ひとしおだった。また初めての出会いから、いろいろな縁がこれほど広がってゆく不思議さを思うと、柳先生にはよくよく感謝しなければならない――そんなことを思いながら、「そうそう、梅見にも行く頃だな」と思うのだった。
|