第2話 空想の世界へのいざない――漢字「雲」をめぐって
広い野原にごろんと寝そべって、青空を、ただただ眺めて過ごしてみたい……
だれだって、そんなふうに思ったことがあるだろう。その空は、真っ青な日本晴れでもいいけれど、白い雲がぽかりと浮かんでいたら、なおのこといい。流れゆく雲をなんとはなしに目で追いながら、どうでもいいようなことをぼんやりと考えていれば、日ごろのストレスもどこかに消えてしまおうというものだ。
空というキャンバスに、雲はさまざまな模様を描き出してくれる。もしも雲がなかったら、空の〝癒やし〟の効果は、ほとんど半減してしまうに違いない。
雲は、ぼくたちを空想の世界へといざなってくれるのである。
雨は雲から降ってくる。
そのことは、太古の人類も経験から知っていたことだろう。だとすれば、漢字「雲」に「雨かんむり」が付いているのは、何の不思議でもない。
では、「雲」を構成するもう1つの要素、「云」の方は、どういう意味なのだろうか。
「
実は、漢字が誕生したころには、「云」だけで「くも」を指していた。ところが、しばらく経つと、「云」は「言う」という意味でも使われるようになったのである。
どうしてそんなことになったかというと、当時の中国語では、「くも」を指すことばと、「言う」という意味のことばとが、発音がよく似ていたかららしい。もともとは「くも」を指していた「云」は、発音だけを借りて、当て字として「言う」という意味でも用いられるようになったのだ、と考えられている。
こういう漢字の使い方を、専門的には「
しかし、1つの文字にまったく異なる2つの意味があるのは、混乱のもとだ。そこで、「くも」を指し示したい場合には、「あの雨をふらせるやつの方ですよ」という意味で、「云」に「雨かんむり」を書き加えて、「雲」と書くようになったのである。
以上が、漢字「雲」の成り立ちなのだが、それでは、「云」はどうして「くも」を指すのだろうか。
この点について、前回も紹介した、1世紀の終わりごろに作られた漢字の辞書『
「云は、雲の回り転ずる形に
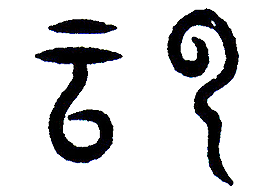 つまり、「云」は水蒸気が渦巻いているようすを描いた絵から生まれた、というのだろう。この辞書には、図のように「云」の古い形も2つばかり載せている。それらを見ると、なるほど、そういう気がしないでもない。
つまり、「云」は水蒸気が渦巻いているようすを描いた絵から生まれた、というのだろう。この辞書には、図のように「云」の古い形も2つばかり載せている。それらを見ると、なるほど、そういう気がしないでもない。「云」の成り立ちについては、以後ずっと、基本的にはこの説が踏襲されてきた。しかし、それに反旗を翻したのが、現代日本の漢字学者、白川静である。白川説によれば、「云」は、あの伝説の霊獣、竜のしっぽが、くるりと曲がって雲の下からのぞいている形だ、というのだ。
「ほんとかいな!」と思われるかもしれない。が、白川漢字学には壮大な大系がある。古代文字では形が似ている「旬」や「九」なども竜に関係すると考えるのだから、「云」もそう読み解くのがふさわしいのだ。
とはいえ、正直なところ、あまりにも「できすぎ」という感じもしないではない。
学説としての当否はぼくに判断できることではないが、白川漢字学の「云」の解釈がすばらしくファンタジックであることは、間違いなかろう。
雲は、人びとを空想の世界へといざなってくれる。
雲を見上げるカリスマ漢字学者は、そこに、風雨を巻き起こしながら天高く昇ってゆく竜の尾を見た。そうして、中国古代の人びとの竜神信仰に思いを馳せた。――それは、いかにも雲にふさわしい、ドラマの一場面ではなかろうか。
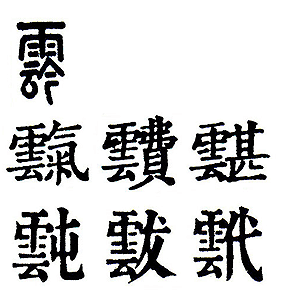 ところで、「雲」の部首は何ですか? と聞かれたら、だれだって、「雨かんむり」だと答えるだろう。しかし、『説文解字』では違う。「云」なのかというと、そうでもない。驚いたことに、この辞書には「雲」という独立した部首があるのである。
ところで、「雲」の部首は何ですか? と聞かれたら、だれだって、「雨かんむり」だと答えるだろう。しかし、『説文解字』では違う。「云」なのかというと、そうでもない。驚いたことに、この辞書には「雲」という独立した部首があるのである。となると、部首「雲」にはほかにどんな漢字があるのかが、気になるところだ。ただ、残念なことに、『説文解字』の部首「雲」には、たった2つしか漢字が収録されていない。1つはもちろん「雲」自身で、もう1つは、図の1段目のような漢字である。
これは、「雲」と「今」を組み合わせたもの。音読みは「いん」で、意味は「雲によって日がかげる」ことだという。つまりは、「陰」と読み方も意味も同じ。たしかに、「陰」の右側は「今」と「云」に分解できる。それに「阝(こざとへん)」を組み合わせるか「雨」を組み合わせるかだけの違いである。
部首「雲」は、『説文解字』の専売特許ではない。11世紀に編纂された、『
この辞書では、現在ではふつうは部首「日」に分類する「曇」なんて漢字も、部首「雲」に入れている。そのほか、部首「雲」には、たとえば図の2段目のような漢字が並んでいる。音読みすると、「氣」と組み合わせた漢字は「き」、「費」と組み合わせた漢字は「ひ」、「甚」と組み合わせた漢字は「たん」となる。
「雲」と何かを組み合わせた漢字は、18世紀のはじめに作られた『
こうやって並べてみると、「へえ、こんな漢字もあるのか!」と思わせて、なかなか壮観ではある。ただ、これらの漢字の意味となると、はなはだ心もとない。たいていは「雲貌」つまり「雲の状態」を表す漢字だ、とだけ書いてあって、それ以上の説明はないのである。
これらの漢字はすべて、日本語の「ふんわり」「ぽっかり」「もやもや」などのような、雲の状態を表す擬態語なのだろう。それを書き表すために、まずは発音が似た漢字を借りてきて、例によって「仮借」の用法で当て字をした。その上で、「雲の状態」であることをはっきりさせるために、「雲」を組み合わせたものだと思われる。
その証拠に、これらの漢字の音読みは、なんのことはない、組み合わせた漢字の音読みとそっくり同じなのだ。
しかし、「雲の状態」専用の漢字に、そんなに使い道があろうとは思われない。せっかく作られた漢字だが、あまり活躍の場もないままに用いられなくなり、やがて、雲のどんな状態を指していたのかもよくわからなくなってしまったのである。
とはいえ、例外的に長く使われ続けた漢字もある。それは、「雲」に「愛」「逮」を組み合わせた、「靉」と「靆」である。
この2つは、ふつう、「
WEB連載だから、こころみに「青空文庫」のホームページで、「靉靆」を検索してみよう。泉鏡花だの菊池寛だの夏目漱石だのといった、錚々たる文豪たちが、この熟語を使っていることがわかる。中には、この2文字で「たなびく」と読ませる例もある。「靉」と「靆」は、少なくとも近代の日本語では、現役の漢字なのである。
ただ、「靉靆」には、ちょっとおもしろい使い方もある。それは、この2文字で「めがね」と読ませる用法だ。
眼鏡は、西方から伝わった道具らしい。15世紀には、中国でも用いられていたという記録があるという。そして、そのころの呼び名が、「靉靆」なのだ。それは、アラビア語か何かに当て字をしたものだと考えられている。これまた、例の「仮借」の用法の一種である。
とはいえ、眼鏡は、雲とは関係がない。それなのに、わざわざ「雲」の付く画数の多い漢字を当て字に使ったのは、どうしてなのだろうか?
16世紀の人、
「
「靉靆」とは、雲が軽くたなびくようすを指すことばである。軽くたなびく雲が太陽や月を隠しても、その輝きまでは覆いきれない。眼鏡だって、それと同じだ。目の前に置いても、ものが見える。だから、「靉靆」というのだろう、と。
これまた、「ほんとかいな?」ではあろう。ただ、もし、眼鏡をかけるということが、眼の前に雲をたなびかせることなのだとしたら、それはそれで、実にたのしいことではあるまいか?
そんな空想にふけりながら、30年来つかず離れず、わが鼻の上に鎮座している眼鏡に、軽く触れてみるのである。
